新型コロナウイルスへの提言
沖縄は本州より1ヶ月ほど感染状況が先行する傾向があり、早くからパンデミックへの対応に追われてきた。その沖縄でコロナ対策の中心的役割を担ってきたのが高山義浩医師。他のエリアの施策への参考になればと、沖縄の取り組みをいち早く全国に発信。厚生労働省の参与として国の施策にも関わってきた。 今回のパンデミックで、沖縄の医療界は “オール沖縄”の体制を組み臨んだが、それでも「5波」以降は人口10万人当たりで全国トップレベルの感染者が出てしまう。高山医師は、「患者を支えた最後の砦は、医療ではなく介護現場だった」と、高齢患者のケアにあたった当時の介護職の奮闘をねぎらう。「医療か、経済か」と2つの対立軸で議論されることが多かった状況に、高山医師は、経済も重要だが、人々の暮らしをどこまで制限するのか、何を大切にするのか、「人権」の視点から考える重要性を訴える。そしていま必要なのは、「次のパンデミックへの備え」ではなく、コロナであらわになったこの社会のほころびを、いますぐ直すこと、と語る。
ProfileView More
東京大学医学部保健学科、山口大学医学部医学科卒。国立病院九州医療センター、九州大学病院、JA長野厚生連佐久総合病院を経て、沖縄県立中部病院で感染症内科と在宅医療に取り組む。今回のパンデミックでは病院での診療のほか、厚生労働省参与、沖縄県政策参与としても地域の感染対策に取り組んだ。
Profile
東京大学医学部保健学科、山口大学医学部医学科卒。国立病院九州医療センター、九州大学病院、JA長野厚生連佐久総合病院を経て、沖縄県立中部病院で感染症内科と在宅医療に取り組む。今回のパンデミックでは病院での診療のほか、厚生労働省参与、沖縄県政策参与としても地域の感染対策に取り組んだ。
Clip.01“オール沖縄”で挑んだコロナ医療体制
●感染症内科医としてパンデミックをどう捉えたか 2019年の12月の末に「中国で何かが起きているらしい」という噂はもう流れていて「なんだろうか?」と。だけど、こういう話って時々あるから、そういう噂の中の一つだろう、とは思っていたんですけれども、2009年の新型インフルエンザの時も、メキシコでは致死率が非常に高いということで「かなりまずい感染症が起きたんじゃないか」っていうふうに言われていました。ところが実際には蓋を開けてみると、それほど従来のインフルエンザとの違いはなかったわけなんです。 ですから、その中国での噂も「本当にこんなに重症度が高いのかな?」と思いながら見てたんですけど、そこでダイヤモンドプリンセスが、最初、那覇港に入港したんですよ。私は感染対策のことで乗船もしたんですけれども、そこで見たことはかなり震撼(しんかん)すべきことで、まずは感染力の強さですね。船という特殊な環境ですから、一般社会における感染症と比べて感染力をどのように評価していいのか私も測りかねるところはあったんですけども、とはいえあれだけの感染者を出して、重症化する人たちも高齢者を中心に一定数いたというところを見ると「これはただ者じゃないな」っていう印象を持ちました。 特にダイヤモンドプリンセスから、例えば名古屋まで患者さんを搬送すると、その搬送中のバスの中で状態がどんどん悪化する人たちがいるというのもインフルエンザでは考えられないことだったので、そういう意味でダイヤモンドプリンセスは多くの人がおっしゃるように、私にとってもこの問題の深刻さに気づかせるものだったと思います。その後の県内での流行は、事前にダイヤモンドプリンセスなどから得ていた感染力や重症度の情報に沿ったもので、その意味でダイヤモンドプリンセスは非常に重要な意味を持っていたなと思います。 ●“オール沖縄”で一致団結した医療体制を組んだ 基本的には大きな流行が起きた場合の体制を整えることについて、沖縄県の医療機関が集まって議論をしていました。ですからまずは当然、感染症指定医療機関であるうちの病院とか、琉球大学病院とか。そういう主立ったところで対応していくということが前提なんですけど、それで絶対に支えきれるものではないと。ダイヤモンドプリンセスを見ていれば。中部病院だって550床の病院ですけれども、割くことができるのは50床から100床。そんなの“焼け石に水”の状態になっていくわけですよね。ですから、“オール沖縄”でこのコロナ=新興感染症と対応していくための体制はどうやってとっていこうか、ということが最初の段階での議論だったと思います。ただ、幸いなことに、沖縄に関して言うと、全ての急性期病院が「うちも診るよ」という姿勢をとりました。ここはやっぱり沖縄の歴史がもともと本土と離れているがゆえに「自分たちでやらないと仕方がない」というところがみんなわかっていて、それは離島の宮古とか八重山とかの病院もそうですけど。そういう病院が多いと、自然、みんな逃げることなく対応するというところで、一致団結できていたというのは、沖縄はよかったなというふうに思いますね。 若者に関しては、それでも重症化する人もおられましたけれども、どんどんバタバタと倒れるというほどの感染症ではない。一方で、高齢者にとっては非常に危険な感染症だというところが見えてきたのも2020年の第2波を過ぎたぐらいだったのかなと思います。 ●流行が1ヶ月先行する沖縄の状況を全国に発信した 保健所がしっかり疫学調査をしてくれたのは大きかったと思います。沖縄においても保健所は、本当に当初は大変だったと思いますけれども、感染者一人一人に対して、いわゆる「積極的疫学調査」ですよね。感染者を拾うだけじゃなくて、その周囲にどれぐらい感染者がいるのか、あるいは誰が感染させたのかというところまで明らかにしていくことで、感染力についても私たち臨床側にフィードバックしてくれましたので。これは本当に助かったことでした。 私も厚労省のアドバイザリーボードにも出席させていただいて、政府の議論を見ておりましたので、この流行の波の立ち上がりの早さに対して、政策決定の判断は、数週間とか1ヶ月とかの遅れがあるんですよ。沖縄県は全国でもやっぱり流行の立ち上がりが、季節的な要因、気候的な要因もあって早い傾向があるので、大体において、政策決定の決断までのインターバルの間がもがき苦しむ。ただ、そのあたりを尾身先生や脇田先生がよく理解してくださって。アドバイザリーボードで毎週沖縄県の状況を報告するように言っていただき、2021年の6月からだったと思いますけれども、私はアドバイザリーボードで「沖縄県の疫学情報とこのような取り組みをしています。こういうことで困ってます」っていうところをご説明する機会をいただけたのは本当にありがたかったです。 流行の規模って階段状に必ず大きくなっていくので、だいたい疫学報告って早くても1週間前、2週間前の流行状況をもとに「いま何をすべきか」って考えるんだけど、それは2週間前に何をすべきだったかの議論なんですよね。沖縄県の議論を聞いていただくことによって、1ヶ月後に何をすべきかの議論に切り替えていただくことはできたんじゃないかなと思います。
Clip.02 “第5波”で浮き彫りになった、ワクチンと治療薬の“効果”
●医療・介護現場でのパンデミックとの闘い コロナの診療自体は、当時まだ2020年の段階でいうと、人工抗体薬、特効薬も出てきてないので基本的には酸素投与をしながら適宜ステロイドを投与してという形で命を支える診療ですから、あんまり“高度な先進医療”ではないんですよコロナの診療は。ですから、ある程度基本の内科医療を理解している先生であれば、コロナの入院医療はできたと思います。 ただ、一方で特殊だったのが「院内感染対策」。これは今までやったことがないという病院も多かったと思うんですね。ほぼ「空気感染対策」に準じた「エアロゾル感染対策」をとっていくとなると、あの当時、病棟を完全に覆ってしまってナースステーションと隔離して、そしてカーテンを下ろして風の流れを制御するとか。多少複雑なところがありましたよね。沖縄県でも2020年の4月ぐらいだったと思いますけど、近隣の医療機関から中部病院に見学に来ていただいて「うちの病院ではこんなふうにやってますよ」というものを見ていただいて。その上でそれぞれの病院で真似してやっていただくというようなことで広げていく必要がありました。 第5波、2021年の7月から8月にかけての流行っていうのが極めて深刻だったと思います。本格的なパンデミックとの闘いっていうのは第5波でしたよね。第2、第3波と繰り返すうちに、沖縄県に関して言うと、全ての病院が入院医療を提供できる体制に切り替わっていたんですけども、その切り替えが追いついていなかったのが高齢者施設でした。高齢者施設はまだ「発生したら全部病院に運べば何とかなるんじゃないか」と思っているところが多く、軽症者も含めて全部運ばれるとすぐに病院がパンクするというような状況だったんです。 一方で、国の方はまだ態度が不明瞭で、軽症者であればホテル療養を認めるけれども、高齢者に関しては全例入院というスタンスをとり続けていたところがあって、「これ、早晩パンクする」と私たちは思ってたので、第2波の頃から高齢者施設に対しては、「軽症者については施設内療養を前提としてください」というようなことをお願いしながら、また、支援に入って施設内のゾーニングの取り方のアドバイスなどもさせていただくということをしてたんですけど、高齢者施設の感染対策が普及できたのは第5波以降なんですよね。第5波というのはどんどん高齢者施設でアウトブレイクが起き始めたわけなんですけど。その一部の高齢者施設は、とにかく中部病院あるいは近隣の医療機関に運んで、「コロナだから引き取ってください」という話になってパンクしかけたっていうのが第5波の時でした。 ●第5波で浮き彫りになった、ワクチンと治療薬の効果 もう一つ第5波の特徴というのが、ワクチン接種がまだ十分に普及していない。2回目のワクチン接種まで進めていない高齢者が多かった。中には高齢者施設でちょっとのんびりしていて、半分にもいってないような施設もあったりしたんですね。その後の第6波、第7波っていうのは、とりあえずみんながワクチンをある程度打っているという状態でのコロナとの闘いだったんですけど、第5波に限ってはワクチンを打ったことがない高齢者が続々と感染したりということも起きていたので、とにかく重症度が高かった。 あの時に私たちはワクチンを打てている高齢者の感染者と打ててない高齢者の感染者の両方を診ているので、いかにワクチンというのが重要だったのかって痛感しているんですよね。それが第5波です。第6波、第7波になるとみんな打ってるのである意味ワクチンのありがたみっていうのがわかりにくくなっていく時代です。だけど、第5波の時に本当に、(ワクチンを)打ててない高齢者施設がいかに感染が急速に広まり、死亡者が次々に出るのかっていうことを痛感したんですよね。 だからあの時代にコロナとの闘いに前線に立っていた医療者と、その時はコロナを診ない、診ていない医療者ではワクチンに対する姿勢に温度差があります。一部にはやっぱりワクチンに対して非常に懐疑的な医療従事者もいらっしゃいますよね。そういう方々は大体において第5波を知らない。そこはあの時の経験をしてる医師が、どうしてもね、そのコロナに対して批判的な医師に対して激しい怒りをぶつける方もいらっしゃいますよね。それは逆もしかりなんですけど。あの軋轢っていうのはやっぱりね、第5波の時に闘った本当にあの時に苦しい思いを高齢者施設と共有した医療者にとって、一緒に闘った仲間を大事にしたいっていうことと、あの時、ある意味“恩人”とも言えるワクチンを現場も知らずに批判することに対しての、非常にこの強い感情が出てきてしまうんですよ。それくらいあの時はつらかったです。 高齢者施設であれ病院であれ、中にはやっぱり当時からワクチンに対して非常に懐疑的な方がいらっしゃる。これは新しいニーズだから私は当然だと思うんですけど。懐疑的であるがゆえに、入所者に一切ワクチンを打たせてない施設もあったりしたんですね。そういうところで感染が広がると、もう本当にたくさん亡くなるんですよ。支援に入って、その入所者にもうアウトブレイクが始まった段階でワクチンを打ち始めたりするんです私たちは。というのがアウトブレイクって1ヶ月くらい続くので、だから始まった段階で打っても遅くないんですよ。そうすると、すっとこう感染の広がりが収まっていったりということも、私たち経験をしていて、本当に第5波っていうのは独特なものでしたね。 その少し後に9月ぐらいでしたかね、「人工抗体薬」という静注薬が普及します。これが使えるようになったことで、さらに死亡するリスクっていうのが下がっていったんですけど、ただ人工抗体薬って静脈注射なんですね。ですから診療所では使えないんですよ。これがまた実は医療をひっ迫させる要因になりました。これは誰が悪いというわけじゃないです。最初は「入院して使うこと」って厚労省がしたんですよ。だからハイリスク者は全員入院させなきゃいけない状況に陥ったんですね。ただ、それからしばらくして、在宅医療とか外来診療でも使えるようになったんですけど、ただ「登録した医療機関じゃないと使えない」とか、いろいろとこの制度の障壁っていうのがあって。要はこのせっかく生まれた特効薬に対するアクセシビリティが良くなかったんですね。
Clip.03限界寸前の在宅医療 「最後の砦」として闘った介護施設
●在宅医としての葛藤 2021年の8月から9月にかけて、私は在宅医もしているので多い時は8人ぐらいの在宅患者をぐるぐる回りながら病棟で仕事もして。そして在宅で呼ばれたら診に行ったりとか、どこも入院先が見つからないような方について。 その場合に2種類の患者さんが在宅あるいは施設療養を選択するんですね。一つはまだ軽症。だから、「静注抗体薬は点滴したから、あとは在宅で療養していてください」っていうパターン、軽症の方。もう一つのパターンが最重症で、もうお亡くなりになる。この2つのパターンの方々を在宅で私も診ることになって。 だけど、コロナの看取りって、本当に看取りになるかどうかわからないんですよ。その時期を乗り越えると回復していかれるんですよね。そのプロセスで「これ助かるんじゃないですか、先生」って言われた時に、助かるんだけど、だからこそ、入院させた方がいい方っていらっしゃるんですよね。それは酸素の投与が不安定だったりとか、吸痰処置が必要だったりとか、これちょっとCT検査をやって、もう少し精密に調べて、あるいは採血とか喀痰のグラム染色とかいろんな検査をやって、適切な医療を行うことで救命できそうだっていう患者さんを抱えてしまうことが起きるんです。だけどベッドはもう限られている。その中でもう家族も納得して、これ以上は(治療は)やらないってことでコンセンサスに至っている患者の入院のためのベッドをこじ開けるのか。今新たに、新規で感染してもう少しお若い方のためにベッドを準備するのかっていうと、どうしても後者になってしまうんですよね。ですから、これは本当に在宅医としてはつらいもので。がんの患者さんのお看取りが少し早まりそうだとか、もう少し先になりますねというようなこととは全然質の違う在宅医療でした。助かっていくプロセスを、助かりそうなんだけど、ギブアップになってしまうこととかも起こり得てそれは本当に難しかったですね。 コロナ禍における在宅医療って、「ベストの医療」というよりは「医療システムを守るために投入されている」という側面があって、酸素が必要なぐらいの急性疾患だったら、いったん病院で治療して。そしてきちんと全身管理をして、そしてステロイドを投与して。そして酸素がいらなくなったら帰ってくるっていうのが本来あるべき医療じゃないですか。「できたら入院をさせる」ということがベストだと思っていても、私は在宅に行って「運ばないでください」とブロックをするという、非常に矛盾したことを在宅医に求められているということがあって、やっぱり患者さんにとってベストの医療を自分が行えていないんだ、むしろベストの医療をブロックするために私が在宅医をやっているんだということに気づかされた時は、ものすごくこの絶望感というか、なんのためにやってるのかなと非常につらかったですよね。患者さんや患者さんのご家族はもっとつらかったと思いますけれども。やっぱりシステムを守るための。地域医療って何なんだろうというふうには思いましたね。 ●最後の砦は介護現場だった 最後の砦は医療じゃなかったですよ。介護だったんですよ。介護現場の人たちがそれこそ、当時「陽陽介護」みたいな言い方、ご存じないかもしれない。「陽陽介護」っていうのは感染している陽性者の高齢者を、感染している介護者が介護職が仕事を休めなくて、発熱しながら介護し続ける有料老人ホームとかがあって、本当は「医療ひっ迫」じゃなくて「介護ひっ迫」だったんです。さらにその向こう側には、介護職が離職したりとか。あるいは感染して倒れたりとかして、もう介護職が確保できない状態に陥っている施設が出始めたんですよね。その状況になって、悲惨な状態、たくさんの人たちが亡くなっていったのが。ヨーロッパの状態だったと思います。介護職がいなくなっちゃって、そして行くと高齢者がベッドで亡くなっているのを発見するみたいな。そういう状況にならなかったんですよね、日本は。やっぱり介護職の方々の使命と努力、それこそ「陽陽介護」になってもなお看続ける人たちがいて、高齢者を最後まで見捨てなかった。私はその介護職のためにこそブルーインパルスが飛ぶべきだと思っていて。医療者は「お手上げ」って言えたんです。介護職は言えなかった。それは本当に申し訳なかったですよね。 私たちが支援に入ったところで、もう当直も確保できなくなって、看護師や医師がですね、支援に入ってオムツ交換までするようなこともありました。決して介護現場がひっ迫している状態を我々医療側が放置してたわけじゃないです。応援には入ってました。沖縄県庁からも看護師の派遣もしてましたし。 高齢者施設でアウトブレイクを経験すると、そこで感染対策のやり方とかを身につけますよね。そうすると、その人たちを次の高齢者施設でアウトブレイクが起きたところに派遣する。そういう仕組みも沖縄県で作ったんですよね。そういう助け合いの仕組みも作りましたけども。それでもね、やっぱりその若手の医師がアウトブレイクが起きている施設にいった時に、非常に私は印象的だったんですけど、もうそのお風呂、入浴ももうできない。人手が足りないから。その施設の入浴もできない、アウトブレイク起きてるんですよ。食事介助ももう限界だけども、食事介助しなきゃいけない、最後までやんなきゃいけないことですよね。少しずつ仕事を減らしていった時にできることって、あとはオムツ交換を減らすことなんですよね。だからもうオムツに糞尿が溜まっていても、もう1日1回が限界みたいな状態になっていて、本当に高齢者の方々がつらかったと思いますよ。 本当に介護職の方々にもっと光を当てて、このコロナを振り返らないと。 最後に高齢者の命を守ったのは介護現場だと思います。
Clip.04社会の価値はどこにあるか?「人権」から考える
●脆弱な社会を、いま、メンテナンスする 今もう医療従事者の不足っていうのは、コロナに限らず、いま多くの地域で深刻な問題になってきてますよね。ここで「じゃあ看護師の確保を進めよう」って言ったってもう奪い合いの段階に来てます。 だから、しっかり「タスクシェア」を進めていくことが必要です。今、看護師さんたちがしている仕事のうち。看護師でなければできないことなのか、いやいや、これアウトソースしてできることは何かっていうところの整理をしていくってことが必要だと思うんですけども。 とはいえ、やはり人手っていうのは限られてるわけですよね。いまいろいろな職場でDXというのが進められていると思うんですけど、それは人手不足がどんな業界でだって起きているからこそ、業務の効率化とICT化を進めているんだと思います。 ところが、医療現場ってものすごく遅れてるんです。ものすごく遅れてます。 それはやっぱり職人気質の年功序列だからだと思います。つまり、前線で頑張っている医師や看護師さんたちの、ボトムアップ型の組織改革って進みにくいんですよ。職人気質だと。現場にはあまり立たなくなったような人たちが組織の方針を決定している傾向があります。 これは本当にDXが進みにくい要因なんですけど、間違いなく今後少子高齢化はさらに進んでいく中で、このDXを進めていかないと、進まなくなると思います。これはもうコロナ禍で僕たちが気づいたことのはずなんですよね。例えば「発生届」をFAXでやりとりしてたら、もう数千人、数万人と感染者が出始めた時にパンクしたわけですよね。 それを、沖縄ではそのDX化が非常に早く進んだんですね。本当に早い段階から「もうFAXはやめましょう」ということで進められたんですけど、個別の医療機関の中で看護師さんの業務を見ていた時に、AIに任せられる部分、タスクシェアが進められる部分、そういったところの効率化っていうのは大事な問題だと思います。これはもう一番言いたいことですね。 そして住民側も変わっていく必要があると思います。「全部を救急医療をやっている病院に行けば何とかしてくれるはず」まだそういう感覚が残ってるとすれば、まずそこを改めて、自分の状態に応じて適切な医療サービスを選択する必要があるし、もう一つ、一般の方々、特に中高年の方々にお願いしたいのは。かかりつけ医を持つということです。 今回のコロナの中で。沖縄は結構医療ひっ迫ひどかったんですけど、一つの要因として、かかりつけ医を持たずに基礎疾患を放置している人がこんなにいたのか。ということがありました。コロナの治療が終わったのに、糖尿病のコントロールがまだついてなくて退院できない人とか、あるいはアルコール依存があって、そのアルコールを抜くための治療がまだ必要ですとか。それをコロナが発掘するんですよ。私は「コロナ入院の人間ドック化」って言ってるんですけど。これは全国にもおそらく当てはまることだと思うんですけど、かかりつけ医を持って日頃の健康管理をしておくということが、医療ひっ迫を軽減することにつながりますので、お願いしたいと思います。 コロナ禍で私たちの社会の脆弱(ぜいじゃく)な部分というのが明らかになりましたよね。 いま沖縄県でもそうなんですけども、コロナ禍で脆弱だとわかったところのメンテナンスをしましょうと。これは決して「次のパンデミックへの備え」じゃなくて「いま私たちの社会でやるべきこと」がわかったんですよ。そういう考え方が必要だと思うんです。さまざまな社会的負荷に、私たちの福祉というものはさらされているわけですから。そこに対するレジリエンスを高めるために何をすればいいのかってことをコロナが教えてくれたわけですから。それをしっかりいま取り組んでいくということが必要になったと思います。 ●社会の価値はどこにあるのか?「人権」から考える 検証をする前にやるべきことは、私たちの社会の価値がどこにあるのかということをきちんと話し合うことからスタートしなければいけないと思います。 多くのマスメディアの方々は、このパンデミックの最中に、医療と経済の対立、対立軸で議論をされていました。沖縄でも「観光をどうするんだ」も含めて、医療と経済をどう優先順位を付けるみたいなことに、どうしても議論がいってましたよね。もちろん経済も大事なんですけど。ただ一方で、経済の軸で議論をしていると、学校に通えなかった子どもたちの苦しみとか。あるいは面会を閉ざされてしまった高齢者施設の入居者の方々の悲しみとか。そういったものが置き去りにされちゃうんですね。これは経済では捉えられない問題です。だけど、非常に重要な問題だったはずなんですよ。 本当に私たちは医療が経済上の対立軸で議論していてよかったのか、むしろ私は「人権」だと思うんですね。私たちが暮らしていく上で大切にしているものを優先させたい。それは「自由」の問題ですよね。それは人権をどこまで保障するのか。それをどこまで制限せざるを得ないのか。公共の安全のために、感染対策の強化のために、自由をある程度制限させていただいたんですよ。それを行政用語で言うと「要請」という言い方をしていて、「いや義務でもないし、強制もしてません」と。要請に対して協力いただいたんです。これ私、詭弁(きべん)だと思います。だって、みんな従わされたわけですからね。つまり人権は制限されんですよ。だからこそ、あの時のコロナのことを振り返る時に、どこまで私たちの社会は人権の制限を求めざるを得ないのか、というところの議論から積み上げていかないと、それは社会においてまず議論すべきことであって、その上で感染症の専門家、公衆衛生の専門家、臨床医の私たちにどのようなミッションを与えるかということだと思います。
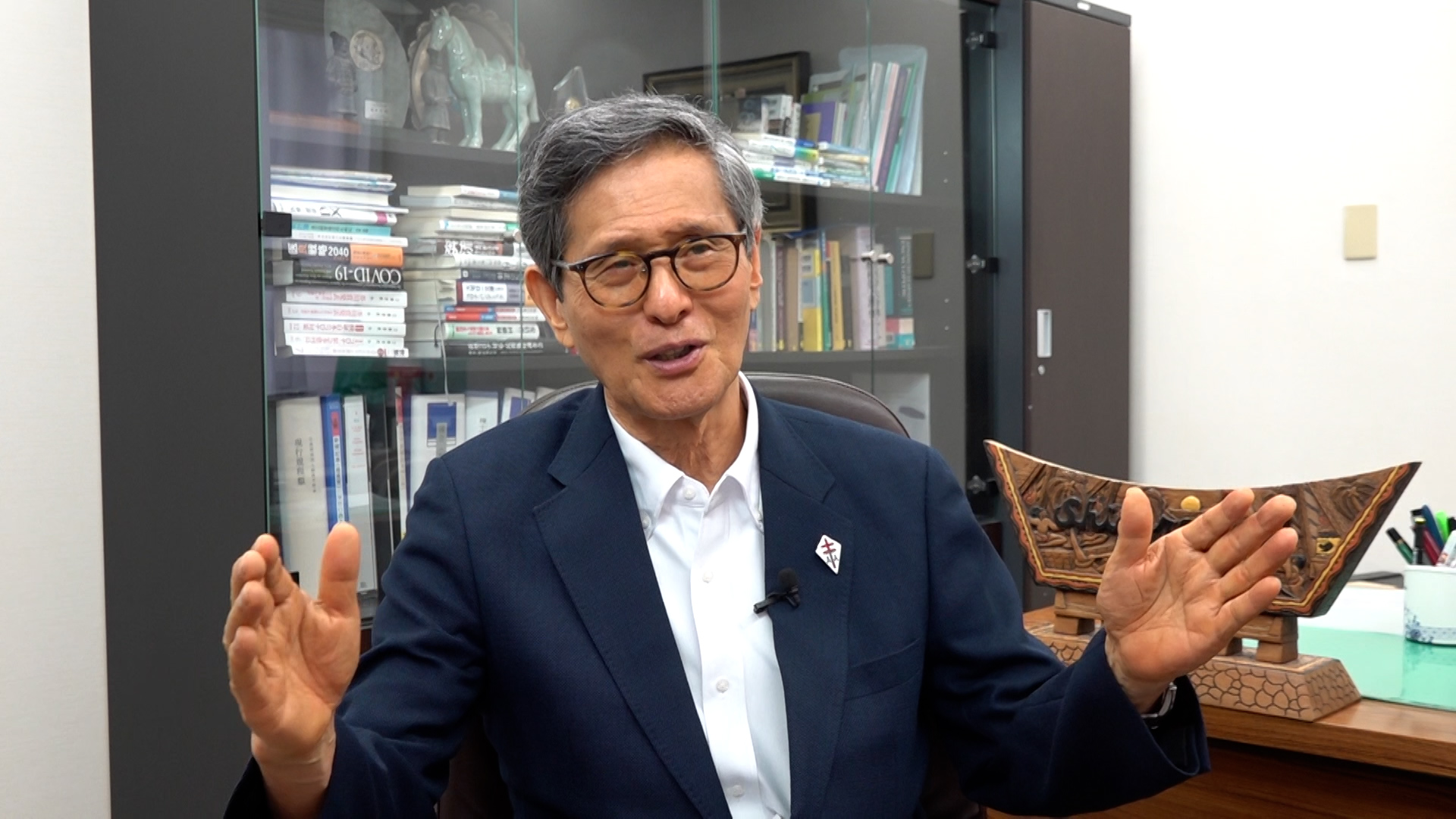
- 新型コロナウイルス感染症対策分科会 元会長
- 公益財団法人結核予防会 理事長
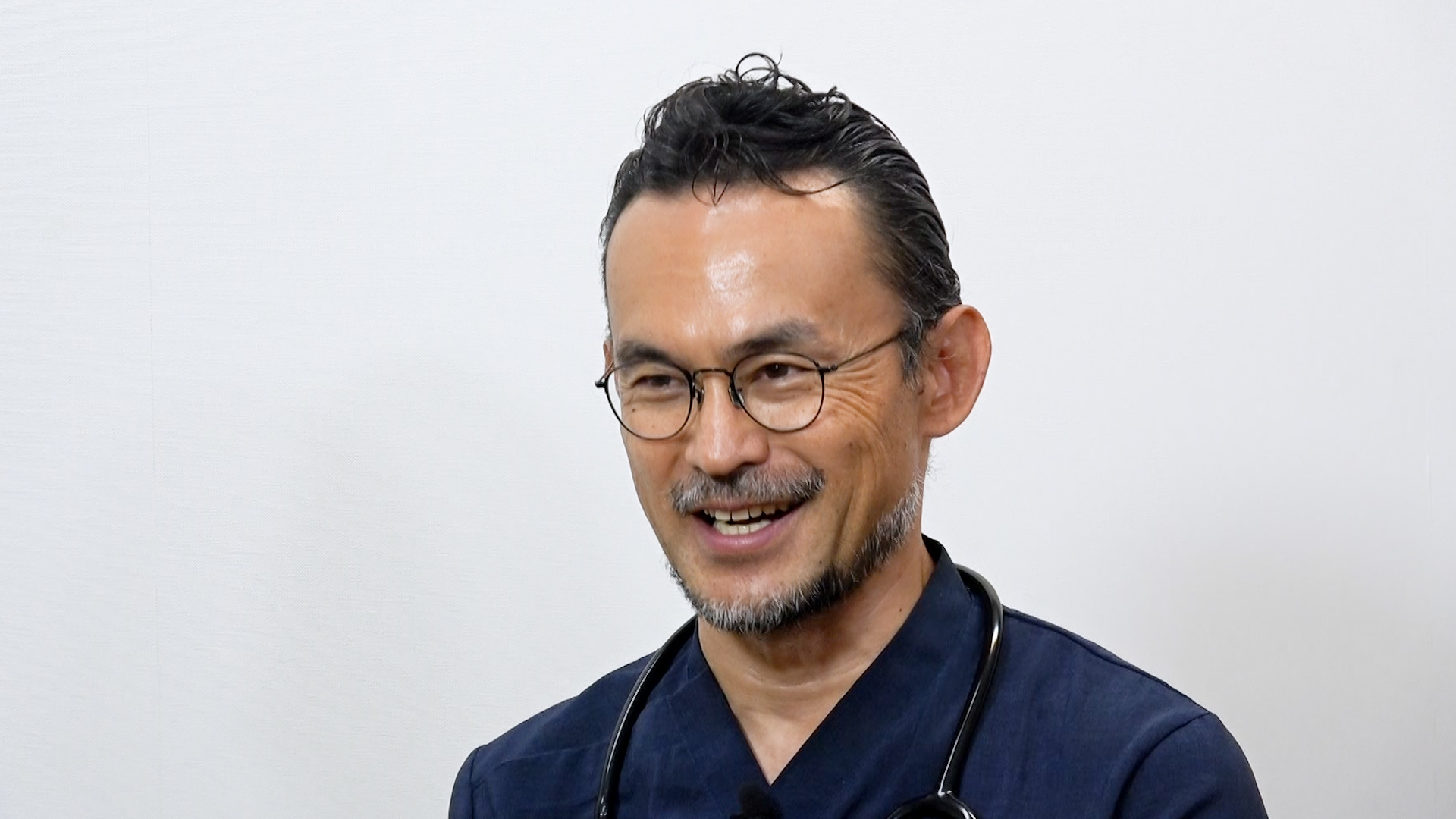
- 医療法人社団 悠翔会 理事長
- 訪問診療医
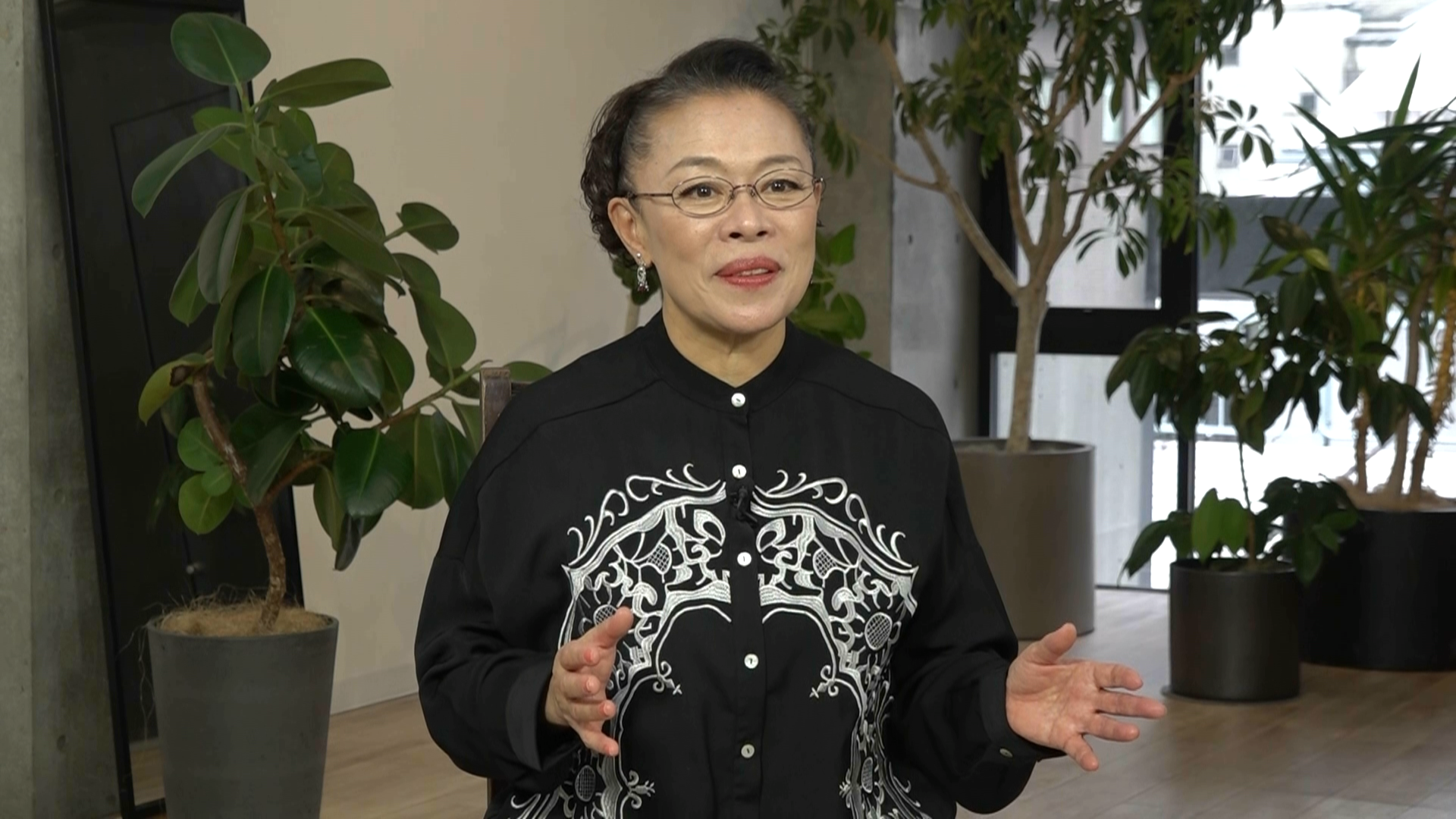
- 俳優・タレント
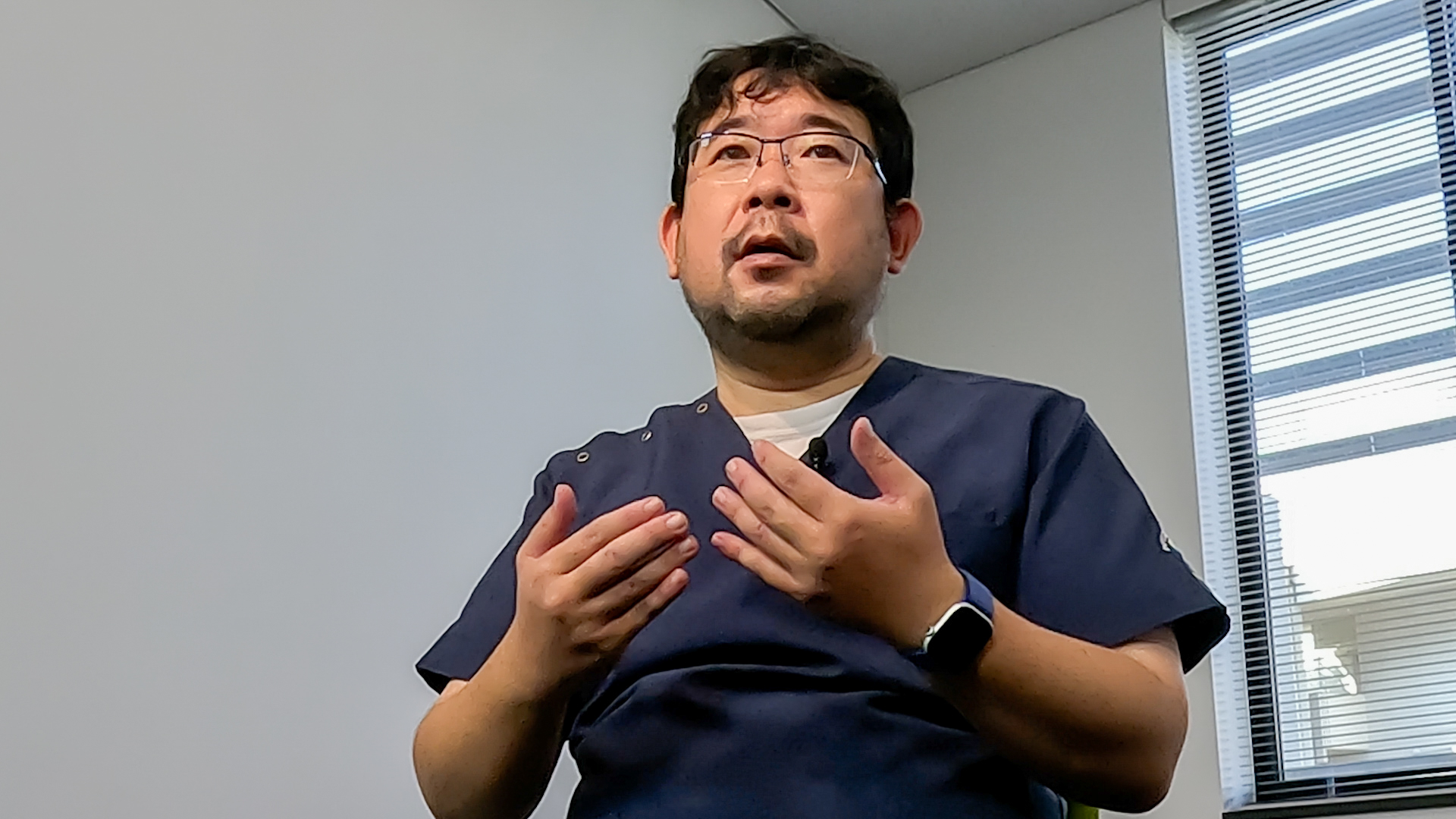
- 大阪大学医学部附属病院 感染症内科 診療科長
- 大阪大学大学院医学系研究科感染制御医学講座(感染制御学)教授

- 国際医療福祉大学医学部感染症学講座 代表教授
- 同 成田病院感染制御部 部長
