新型コロナウイルスへの提言
2019年に中国武漢で発生した新型コロナウイルス。これまでにない特性がパンデミックにつながった▽エアロゾル感染、無症状で広がる伝播力にどう対処するべきだったか?▽広くメディアを通じて伝えたかったこと、伝わりにくかったことは▽医療崩壊の危機その時専門医が感じたこと▽ワクチン定期接種はなぜ必要なのか?▽次のパンデミックのための備え方など感染症専門医としてコロナ5年のいま伝えたいこととは?
ProfileView More
1987年長崎大学医学部を卒業後、同第二内科に入局。米国ハーバード大学留学後、東邦大学講師、東京医科大学主任教授を経て、2018年から現職。日本感染症学会理事長、日本臨床微生物学会理事長、日本化学療法学会前理事長、日本環境感染学会理事。PMDA委員、AMEDプログラムスーパーバイザー、東京都iCDC専門家ボード感染制御チームリーダー、厚生労働省医療用医薬品迅速・安定供給部会 部会長代理等も兼務。
Profile
1987年長崎大学医学部を卒業後、同第二内科に入局。米国ハーバード大学留学後、東邦大学講師、東京医科大学主任教授を経て、2018年から現職。日本感染症学会理事長、日本臨床微生物学会理事長、日本化学療法学会前理事長、日本環境感染学会理事。PMDA委員、AMEDプログラムスーパーバイザー、東京都iCDC専門家ボード感染制御チームリーダー、厚生労働省医療用医薬品迅速・安定供給部会 部会長代理等も兼務。
Clip.01新型コロナウイルスはなぜ感染拡大したのか ウイルスの特徴を知る
これまでさまざまな感染症が人類を襲ってきて、そして本当に多くの被害が出てきたわけですね。いままでいろいろなウイルス、細菌にしても、基本的には例えば「飛沫感染」とか、あるいはもう一つは「接触感染」ですね、こういったものが中心になるんですけど、いままでになかった「エアロゾル」というものですね、単なる飛沫ではなくて、もっと空気中をふわふわ浮いて多くの人に感染させる力があると。そういうようなタイプの感染力の強さということを考えますと、いままでに類を見ないような性質を持っているウイルスであろうと思います。 例えば、他のいろいろな感染症も広がりましたけど、「3密」なんていうような言葉はなかったわけですよね。何でわざわざ「3密」っていうのを避けなきゃいけないの?それはやっぱり感染が広がりやすいような状況がそこで作られるということですけど、それは単純に今までのいろいろ飛沫感染、接触感染だけでは説明がつかなかった「エアロゾル感染」というのがあって、そのために空間に広がりやすい。それをなるべく防ぐためには換気をしましょう、だとか、なるべく狭いところに集まらないようにしましょうだとか、そういったことが対策の一つになってきましたので、それはやっぱり今までになかった概念だと思います。 インフルエンザの場合はだいたい多くの人が、感染したら症状が出ます。そして発症して、熱は高いし、筋肉痛、関節痛、典型的な症状が出ますので「この人は感染している」とだいたいはわかるわけですね。そうすると、封じ込めようと思ったら、ある程度その症状がある人をしっかり抑え込めば、対応はできないことはない。その一方で、新型コロナウイルスというのは「無症状」の人もいる。そして発症する場合も、発症する数日前から感染力があるということになると、やはりインフルエンザとは性質が違うし、見つけにくいし、広げやすいという部分があると思います。 インフルエンザはだいたい、その発症の1日前から感染させるリスクはあるだろうと。ただ、コロナウイルスは2、3日前ぐらいだろうということですけれど、コロナの場合はちょっと喉が痛いぐらいとかいう程度の、あるいは熱もそれほど高くないとかいうふうで、正直自分がコロナウイルスに感染したってことを自覚することの難しい感染症でもあるんですね。だいたい症状がある人が検査して陽性になるというので、今まで私たちは対応してきましたので、まさかその接触している人の中で無症状の人を調べてみたら、その人たちの中から陽性者が出るって考えていなかったわけですよね。 最初の頃はPCRというのがかなりいろいろ検査でやってまして、ウイルスの量というところまで測ることができたんですね。そうすると、例えば無症状の人のウイルス量っていうのは低いのかっていうと、そうでもないんです。無症状でもかなりの量のウイルスを出している人がいるんですよね。それだけはやっぱり個人差が大きいと。症状がある人がどんどんウイルスを吐き出して、無症状の人は少ないと言うのであれば理解ができるんですけど、その点においても、私たちが考えてる常識を覆すといいますか、無症状の人でかなりのウイルスを持っている人がいるというところもこのウイルスの特徴だろうと思います。 海外でウイルスの感染症が発生して、新しいもので、だいたい少なくとも日本の場合は「国の中に感染症を入れない」というような、いわゆる水際対策ですね、これがなんとかうまくいけば、ある程度の規模でおさまるだろうと。それが例えばSARSはあれだけ、一応アジアでも多くの感染者が出たんですけど、一応日本には誰も感染者は国内では感染者はいなかったということになっています。それもそうなんですね。すなわち、コロナウイルスの新たなものができても、必ずしも全世界で感染が起こるわけじゃない、日本では起こらなかったということで、最初の頃「また新たなコロナウイルスの病原体が出た」と。ただ、おそらく国内には持ち込まれはするだろう、だけれども、ここまでの規模の感染拡大になるとは思ってませんでしたし、だいたい通常は1、2年ぐらい、長くても1、2年ぐらいの間には終息するだろうし、それまで多少世の中緊張状態になるかもしれませんけど、やがては落ち着くだろうと考えていたわけですけど、やっぱりこのウイルス、後半になって出てきた「オミクロン株」ですね。これが今までとまたさらに特徴を変えて襲ってきましたので、だから結局5年経った今でもですね、まだまだ流行を繰り返してるわけですけれど、それが他のいろんなウイルス感染症とは違う特徴でもあると思います。 最初の頃、第1波、第2波、第3波と波が襲ってきてですね、その度ごとに受け入れる患者さんも多くなってきたわけですけれど、オミクロン株の流行になってからその要請が桁違いになりました。外来に来る患者数も全然違う規模になりました。なのでまずは数の多さとですね、そしてその中で重症化する方が多くなって、医療機関のひっ迫っていうのを、それまでももちろんある程度対応はしてたわけですけど、その規模を超えてですね、格段に患者さんが増えましたし、そういう意味ではオミクロンは、全然それまでとは規模が違うという状況だと思います。 例えば、その前にありました「アルファ株」とか「デルタ株」とか、あの辺はむしろかなり病原性強かったんですね。例えば50代の男性とか、そういう人達でも、私達の病院に入ってきても、何か急に急変してお亡くなりになるとか、通常はそんな50代、60代で亡くなるってないわけですけれど、それがもう入ってきてすぐに状態が悪化するとかいうようなことが起こってたのが、例えばデルタ株とか。 オミクロンになると、逆に重症化する方の割合は減りました。ただ規模が大きくなったので、全体として比べてみたら、重症者の割合は減ったんですけれども、数からいったら実質的には増えてしまったんです。そしてお亡くなりになる方も増えました。やっぱり病原性はいくら多少低くなったとはいえ、感染の規模が拡大したがゆえにですね、全体としてはやっぱり被害は大きくなったと言えると思います。 ここまでの変異が起こってきて、そしてその度ごとにまた流行を起こして、それがそれぞれちょっと性質が違ってると言うことは、なかなか今までの感染の流行では起こらなかったことですね。例えばインフルエンザもそれなりの規感染規模がありますけれど、毎年一応流行は起こっていますけど、その度ごとにもちろんちょっと性質が違うんです。でもその性質の違いというのは、そんなに極端なものではないんです。ただ今回は短期間のうちにアルファとデルタ、そしてオミクロン、大きく分けるとそんな感じになりますけど、それぞれがかなり性質が違うんですね。ミクロになったらもうかなりそれまでと違って、そのウイルスの性質が大きく変わりましたので、その辺の変化の激しさっていうのは今までの想定外だったですね。
Clip.02無症状と重症化 新型コロナウイルスの特性
例えば、自分の身近の人がお亡くなりになった。そうすると「この病気は怖い病気だ」ということになるわけです。ところが、自分が感染した、でもちょっと喉が痛いし、鼻水、咳ぐらい出たけど治ったよ、というふうになると、「これは風邪だ」というふうになるわけですね。 ということになると、その病気を捉える上で、自分の身に起こったこと、あるいは周囲に起こったことが、ほぼだいたい、この感染症の特徴というのを印象づけられるわけです。だから、人によってはすごい怖い病気でもあるし、一部の人にとってみれば「いやあんなのは風邪と同じだよ」となるし、それが例えばお一人お一人の考え方がそのままそれぞれ維持されるのはいいんですけど、これがSNSで拡散されるわけですよ。 そうするとある人が「あれはもうただの風邪だよ、そんな大したことないよ」というのが、そのインパクトが他の人にすごく伝わっていって、でも他の人は「いやいや、怖い病気なんですよ」っていうのを言うんだけれども、それが人々によってどのように受け止められるか、その受け止め方が様々なわけですよね。 そうすると、すごく社会の中で極端な考え方を持たれる人がやっぱりどうしてもそれで増えてしまうと。「軽くて心配ない病気」と言う人もそれなりにいるし、「いやいや怖いんだ、注意しなきゃいけないんだ」っていう人たちがいるし。ただそれはそれぞれの考え方でいいんですけど、それがお互いにぶつかってしまってですね。 ある意味、衝突を起こしてしまうと。それがそのターゲットがお互いにいく部分もあれば、今度はマスコミに行ったり、専門家で意見を言っている人たちに行ったり、あるいは政府に行くったりとかですね、いろんな人たちにこう自分たちの考えが正しい、でも相手がやってることは間違ってるというふうなことで、だいぶ分断を作ってしまって、この感染症自体が、その捉え方が多様なものですからね。 それが原因によって他のいろんな考え方が衝突し合って、だいぶいろいろな混乱が生じたなと思っています。 例えば、最初の頃はウイルスの性質がわかりませんでしたから、やっぱりそれは捉え方も最初は違いました。何が本当にこのウイルスの捉え方として正しいのかっていうのも、なかなかいろんな論文としてもなかなか上がってこないし、そういう意味では経験値でものを言っているところも多々あったんですね。 そうすると、やっぱり病院の中での感染対策はどういうことをやるべきかっていうのもかなり議論がありました。もう徹底的にやろうっていうところもあれば、そこまでやれないっていうところもあったし、そういう意味ではですね、医療従事者とか専門家の間でも多少最初の頃はいろんな意見が分かれてたというところはあると思います。
Clip.03情報と感染症 正しい情報を広げる方法は?
あの頃は正直わからない部分もたくさんあって。 ただ一応、「基本的にこういう考え方がある程度正しいんじゃないかな」という“確からしさ”のもとにしゃべっていたこともあるんですけれど、正直言って何の“お墨付き”もないわけですね。ただ、基本的にこれまでの感染症の考え方からすると「これが基本的な考え方ですよ」ということで、いろんなところの先生たちが発信していたわけですけど、ただ、正直言って、バラバラな意見の食い違いもあったと思います。 そういう意味では、やっぱり尾身先生が頑張って分科会などで意見を統一していただいて「今のとらえ方はこういう形です」というふうなことで話をしていただいて、これはやっぱりある程度、それをまともにしっかり受け止めていただいた方は、ちゃんと実行していただいたと思うんですけど。 ただ、あれだけのインパクトがある感染症なので、「納得いかない」というよりは、それに対する敵対心だとか、いろんな感情がこもったものが出てきたと思うんですよね。それがゆえに「そのまま受け止められない」というより、不満を持っている人たちは、今度は逆に、全然違うような意見を取り入れるようになってしまった。そこにちょうどSNSが入り込んできてしまったというところもあるので、とにかく、あのときは全く準備ができてなかったんですよ。 なので、みんなが手探りでいろんなことをやり始めていたんですよ。そうすると「これから情報発信するやり方はどうするべき?」なんていうのを話し合ってることもできなかったんですよね。もう、やりながら少しずつ改善していって、いろんな批判をされながら、それに対してまた改善をやっていった、っていうのが最初の頃でしたので。、本来だったらもうちょっと冷静に、ちゃんと情報の発信をみんなに受け止められるような発信の仕方だとか、ちゃんとエビデンスもしっかり出しながらっていうふうなことが考えられたでしょうけど、あのときは、ただ単にいろんな情報が交錯していて、何が本当なのか、わからないままに、ちょっと飛びついたものを広く出していた部分があったので、残念ながらそのときはいろんな情報が玉石混淆で、難しい部分はあったと思います。 でもいま考えてみれば、もうちょっと冷静にちゃんとやれればできたかもしれない。 やっぱりある程度、もうちょっと、例えば関係している人たちが、分科会もそうでしょうし、例えば学会もそうでしょうし、あるいはそれ以外のマスコミもそうでしょうし、連携して「本当に今あるエビデンスの中で言えることはこれなんだよ」ということをもっと統一して出すことができれば、それだったら信じられるんじゃないかなという“よりどころ”になったと思うんですよね。 ただ、もういろんな意見が乱立すると、どれを信じていいかわからない。そうすると自分が信じたいものに飛びついてしまうというところがあったので、多くの専門家もそうだし、もっといろんな人たちが、今の現実に得られるデータからすると「これが正しいんですよ」っていうふうなことを、もうちょっと別の形で発信できていれば、多くの人たちが「だいたいそれだったら納得いくだろう」というふうに信じていただけたんじゃないかと思います。 次はそれを生かして、今度はちゃんとやれるだろうと思います。 正直、統一性に欠けたという部分もあるかもしれません。横と横の連携がなかなかうまくいかなかったというところもありますので、できれば本来であれば、もうちょっと関係する人たちがですね、もう少し密に連絡を取り合って、ある程度集約したものを作り上げるというところが大事なんだろうとは思います。 今言っているのは、学会だとか政府だとか厚労省だとかということになりますけど、多くの医療機関も患者さんに対応したところであるわけですね。その医療機関も正直言って連携がとれてなかったんですね。それぞれ、どちらかというと国が決めた方針に、もちろん多くの病院が従ったわけですけど、ただ、その中でもやっぱり一部の病院はやっぱりある程度のところまで「もう自分たちは診れない」ということで、頑張っても診ない方向で頑張ってたし、あるいは診なきゃいけないというところはもう本当に疲弊しながら診ていたというところもありますけど、これが多くの、例えば医療機関がもうちょっと相互に連携ができていれば、患者さんのやり取りもスムーズにいったでしょうし、医療全体としてのいわゆる仕組みがもっと働いたんだと思うんです。 残念ながら。その後、医療機関側の連携も取れず、例えば自治体との連絡もあまりうまくいかず、そういう中で、もちろん保健所もいろいろ間に入って、相互に混乱しながらですね、最初ドタバタしながらやってたというのが最初のところなので、これももう今、この平時の時に、今後もし起こったらどうするのというふうなところをですね、ちゃんと次に備えるための反省点として生かして、そして次はこうしましょうというようなものを作り上げていかなきゃいけないと思います。
Clip.04医療崩壊の危機はなぜ起きたのか?感染症専門医が現場で感じたこと
日本の医療というのは非常に多くの病院があって、クリニックもあって、とてもアクセスがいいんですね。だから、患者さんはとにかく調子が悪ければすぐ外来を受診できるし、だいたい入院もできるし、というのが今までの医療だったわけですけれど、ただ、それは感染症のような特殊なものではなくて、一般のいろんな疾患なわけなんですね。 ところが感染症となると、ましてや今までになかった感染症となると、誰も基本的には経験がないと。そうなったときに、やっぱりどんなところでも、自分のところで受け入れるというところになると、何がやっぱり懸念されるかというと、自分のクリニックの中、あるいは病院の中から感染者が出るとスタッフが感染すると言うことなんですよね。 そうすると、例えば開業医の先生がお一人感染しちゃったら、そこはいったんは閉じるいうか休診せざるを得ないし、それだけならまだしも、最初の頃っていうのは「あそこの病院から感染者が出たよ」って言われると本当に噂が広まってしまって「もうあそこには行かない」というふうなことで、それぐらい被害が大きく出るわけですね。 そこまでのリスクを冒して自分たちのとこで診なきゃいけないだろうかというふうになると「いや、それは無理だよね」と。「感染症の専門家もうちにはいないし、そんな診れるだけのノウハウもないし」というふうになると、最初の頃に自分たちの病院では診られないよという判断は、それはある意味正しかったんですよね。 ところが、ここまでの勢いで感染者が広がると、もうどこにでもいるようになってしまった。ましてや、普通に全然“ただの風邪”だと思ってた患者さんがコロナになったとか、あるいは入院患者さんで熱が出て調べてみたらコロナだったと。すなわち、どの医療機関もコロナから避けられることは無理だというところまで来ましたので、そうすると、もう無理矢理ではありますけど、経験させられてしまったわけですね。 それが閾値(いきち)をずっと下げていたんですね。コロナというのはもうこんなものなんだ、自分たちの病院の中で感染者が出たとしても、このように対処しようということが経験値として上がってきたので、もう途中からはですね、特にオミクロン株の後になってくると、だいたい多くの医療機関は受け入れざるを得なくなってきたと。 最初の頃のように抵抗する人たちも大部分は減ってきて、最初の頃はもうとにかく「自分の病院で受け入れるなら私は辞めます」ということで、医療従事者そのものも非常に抵抗感が強かったわけですけど、ただそれがだんだん、誰でも感染するような状況になってくると、それに対する抵抗感も下がってきて、「自分たちのところでも診なきゃいけないだろう」ということで、やがては「来ても診られますよ」というふうに、だいぶこの反応が変わってきたなとは思います。 もちろん、受け入れられるだけの能力があって、あるいはトップが「うちでもちゃんと受け入れよう」と判断していただける病院もそんなには最初の頃多くありませんでした。それはもちろん、大学病院だとか地域の中核病院だとか、それはそこの病院の責任ですよというふうな形で、無理やりある程度やらざるを得ないからやっていた、というところがまず最初、患者さんを受け入れたというところになると思いますけど、最初の頃はお一人その患者さんを受け入れるだけでも、病院からすればやっぱり緊張感があったわけですよね。それがだんだん数が増えていって、そして「あそこではこういうふうにやってるみたいよ」っていうノウハウが他の病院にも伝わってきて、だんだんどういうふうにやれば大丈夫なのかということがある程度知識として増えてくると「自分たちのところでもやりましょう」と。 そういう中で、例えば大きな影響があったのが、一つはワクチンなんですよね。 ワクチンが使えるようになったっていうのは、やっぱり安心感を持たせることができましたし、あともう一つは、やっぱり治療薬がいろいろ出てきたというところもあって、そういう意味では最初の頃のように何の対策もできないまま、専門的にウイルスも減らせない。 重症化したらもちろん人工呼吸器につなぐとかいうことはできたとしても、具体的な治療ができないというような感染症から、ワクチン予防策もあるし、治療薬もあるし、あるいは感染対策のノウハウもあるしということで、医療現場はそういったことによってだいぶ変わってきたなと思います。 もし新たな感染症が起こったときに、最初に「どこの病院でも受け入れてください」というのは多分無理だと思います。それはやっぱり特定の病院でしっかり対応する、ということになるとは思うんですけど、ただそれが感染の規模があまりにも大きくなると、例えば「中核病院だけではもう対処できませんよ」という状況になれば、当然他の医療機関の協力も得ないと、極端な話、ご自宅でそのまま、誰も診ないでお亡くなりになるような方が出てくるわけですよね。それはやっぱり問題があるので、患者さんに対してちゃんとした医療を提供するということであれば、広く診られるような形になると思いますけど、やっぱりこれはステップバイステップなんだと思います。 最初はちゃんと診られる病院で診る、そしてそのうちそのノウハウを他の病院にも広げて連携をする。ある意味、感染症が最初の段階では“問題”だとしても、その後何が問題かというと、実はある程度回復した後で、ただ(身体)機能がまだ戻っていない、家には帰れないんだけど例えばリハビリが必要だとか、これはもうちょっとケアが必要だとか、そういう人たちがうまく他の病院に移って、どんどん地域で広く患者さんを診らられる体制ができると、本当に患者さんをうまく配置を変えながら診れるようにできるんですね。これが最初は全然できなかったんです。全然相互の医療機関の連携がとれず、「うちの病院でちょっとここまでの患者さん無理なんで、他の病院に」というふうに紹介しても、「いやあうちは無理です」と。それを一人の患者さんについてあっちこっちの病院に電話して、ようやく引き受けていただくというようなことをやってたので非常に非効率的でした。それが例えば、ある意味もしかしたらこれからデジタル化で、もうちょっと情報共有を、広く多くの病院が同じような情報を共有して、「じゃあこの患者さんを受け入れますよ」とか、そういうふうになってくるといいでしょうし、仕組みも変えないといけないですし、やっぱりそれはこれまで大変な思いをした、あれを繰り返したくないということで、次のステップに移らないといけないんだろうとは思います。 やっぱりうまくいった例というのは、最初は皆さん顔を突き合わせてということになって、それぞれの先生たちの顔を知っていることで「あの先生に連絡をとってみよう」とかいうふうなことで最初やってたわけですけれど、それが例えば途中では、その地域の医療機関がネット上でみんなで話し合いの場を定期的に持つようになるようなところもあったんですね。そうすると、お互いの情報共有がすごく進んだんですよ。お互いの顔が見えて「うちは何名いま受けてますよ」みたいなことが、それぞれ話し合いの場で顔を見ながら言えるようになったというのは、かなりお互いのやりとりができるようになりましたし、それが例えば保健所だったり自治体が音頭をとって「こういうネットワーク作りましょうよ」と言っていただくと、非常にそれが進むことがあるんですね。なので医療機関、「患者を診るのは病院でしょう」「もうその病院で頑張ってください」じゃなくて、その仕組みを作るのはやっぱり自治体でもあり、保健所の後押しも重要だと思います。
Clip.05パンデミックへの対策・伝え方の難しさ
正直言って、例えばテレビとかで発言しても、本来であれば、このことに関して言いたいことは5つも10もあるんだと言うことが、それを例えば10なら10言ったら全体を理解していただいて、皆さん納得していただける。ただ、それだけの時間を与えていただけないのですね。「その中から2つ、3つだけしゃべってください」ということになると、どうしても一部だけしか伝えられないと、 聞く人は、正直、全体像をわかってるわけじゃないので、捉え方が変わっちゃう。 とすると、その捉え方によっても大分違うし、例えば「これは重症化する病気なんですよ」というふうに私が言うとですね、それはなるべく被害を減らしたいし、「多くの人たち、やっぱり警戒してくださいね」というつもりで言う部分があるんですね。 なので「気を抜かないでしっかり感染対策をとってください」という表現をすると、一部の方は「怖い」と。「あんな言い方はしないでくれ」と。「すごく精神的にも、私はそういうふうな発言を聞くと、もう聞きたくない」っていうふうな感じで言われる場合もあるんです。 だけど、「これで大丈夫なんですよ、あまり心配しなくていいですよ」なんて言うと、「じゃあ飲み会に行こうか」みたいな感じになってしまって、行動がそっち側に行くと、これはまた感染が広がるなというのもあって、なので、なるべくならば丁寧に説明をしたい。 だけどそれだけの時間もない、一部分しか伝えられないということで、私が発信する場合は、やっぱりちょっとそこの、何て言うんでしょうかね、「困ったな」というふうに思いながらも、最小限に言えることは言ってました。 ただ、極端な捉えられ方をすることも中にはありますし、海外で、例えばノルウェーにはその専門家がもちろんいて、そしてある程度国の方針に関わっていて、その方針として、例えばあまりマスクだとか、そういう感染対策は徹底しないというふうなことでの方針を出したわけですけど、それは 徹底しないというのは「やらなくていいよ」と言ったわけじゃなくて、「そこまで徹底するのは無理だろう。だから、あまり強制的にはやらない」というふうなニュアンスで言ったのが、それが逆に日本に伝わってきた時には「もうノルウェーは完全に対策をやめた」だとか「感染を広げてもいい」だとかいうふうなことでの捉え方になってたわけですね。 だけど、実際私はその発言を最初にされた人に聞いてみると、「自分はそんなつもりで言ったわけではない」と。それは世界中にそういう全然違った捉え方をして広がったということもありますので、言ったことが歪められて捉えられて、それがそのまま広がってしまうというのが一つの情報伝達の怖さだなと思います。 例えば全然マスクが行き渡ってない。その時に「皆さんマスクしてください」って、それは確かに矛盾なんですよね。でもそれを理解してるからこそ、みんなマスクを絶対しろとは言わないということが、その最初の時のノルウェーの方針だったと言うことですけど、あの時、日本人はもうそんなことを考えず「とにかくマスク」ということでいってましたけど、「どこに行けばマスク買えるんだ?」ということで、みんな苦労していたわけですね。 それらを無視して「マスクしましょう」「絶対だ」っていうなことで打ち出してた。その、だいぶ矛盾もあるんですけれど、やっぱりこのマスコミを介して伝わってくる情報は、必ずしも全部が全部正しいわけでもないというところもあるのかなと思います。 なので、その時その時で基本的には大事だと思ってるのは“バランス”だと思ってるんですよね。「100%こうしましょう」だとか「100%しないでいいですよ」だとかいうのはそれは極端すぎると。だんだん状況も変わってきて、例えばマスクに関して言えば、外してもいいタイミングっていうのは必ずあるんです。ただ、最初の頃かなり緊張してた時は、皆さんがどのタイミングでも常にマスクするっていうのが当たり前のような感じで広がっちゃったので、「そこまでは必要ないんですよ。ただこのタイミングではやりましょう」ということで、それは特にリスクが高い場面ですよね。「リスクが高い場面ではやりましょう。だけど、ここでは感染しないでしょう。だったら、ここはむしろ本当に皆さん外しましょう」というメリハリを付けてやると。それが多くの人たちにとってある程度は納得がいってもらって「しょうがないか、ここではやるか」という感じで受け止めていただければなと思って発言はしていました。 だんだん、パンデミックが起こって1年、2年、たぶん3年ぐらいまでは皆さんマスクされてましたし、その時に私に寄せられてた質問も「いつになったらマスク外せるんだ」と言われてたんですよね。「もうこれからマスクを外せる日は来ないんじゃないか」みたいな感じで言われてたので、「いや外せますよ、必ず」と。 「ただそれが来年になったらすぐ外せるかどうかわからないけれど、でも来年の後半になったら、少しずつ外せるかもしれませんよ」って言ってたんですよね。だからあの時に、何て言うんでしょうね、みんなが非常に落ち込んでたので、このままずっとマスクをし続けなきゃいけない世の中になったんだと思われてもいけないので、「これから先は変わりますよ」と。 それは確かに自信はあったんですけれど、このままずっと感染が同じような状況で続くわけはないと。ある程度必ず落ち着いていくと。ただし、「感染対策は今の時点でマスクをみんな外すタイミングじゃないですよ」というのは言ってましたよね。
Clip.06新型コロナワクチンの効果 インフルエンザとの違いと定期接種の重要性
mRNAのワクチンというのは、今までワクチンというのはいろんな種類のワクチンがあったわけですけど、それまでにないタイプのワクチンだったんですね。確かに 遺伝子を組み替えて、それを人の体に入れるということで、作ること自体は比較的早く作ることができるので、例えば変異株ができても、それに対応するものに作り替えられますし、従来のやり方のワクチンに比べると、短期間に対応することができたと思います。 ただ、それがゆえに、その新しいワクチンに対してどうしても不安感もありましたし、「そんな今まで打ったことのないものを自分の体の中に入れていいのか」ということは確かに多くの人は疑問に思ったと思います。ただ、ちゃんとワクチンのステップという、開発の承認のステップというのがありますから、最初の段階から、例えば動物実験に入って、そして人の臨床も、フェーズ1,フェーズ2、フェーズ3って ちゃんとステップを経て、そのデータをもとに承認ということになりますので、新型コロナのワクチンは、確かに本当に1年くらいで開発ができたわけです。これはもう極端に早いんですよね。ただ、ステップは踏んでるんです。何か飛ばしていきなり承認させたわけではないので、そういう意味ではちゃんとそれだけ短期間でできたっていうのは驚異的な速さではあるんですけれど、ちゃんとした承認されるだけのデータはあったということになって、かつ相当な数の人がワクチン打たれてるわけです。しかも1回じゃなくて、2回、3回ずっと繰り返して打たれてるわけですね。 ただ、どうしてもそれだけの多くのワクチンの接種が行われると、ワクチンというのはその有効性が100%ではないし、有効性だけから見ると、例えば「ワクチンを打ったけど感染する人が出るじゃないか」っていう意味での疑問を生じる人もいました。 特に副反応についても、いろんな副反応が、例えば局所が腫れたり熱が出るっていうぐらいならいいんですけど、アナフィラキシーが起こったりとか、いろんな副反応が起こると、逆にそれがクローズアップされると「やっぱり怖い」と。ましてや、あくまで科学的にも証明されたものですけど、例えば不妊だとか、何かいろんなこんなこと起こりえないだろうという副反応がSNSの方で広がるわけですよね。 それを信じてしまって「やっぱりワクチン怖い」という形で、これもやっぱりある意味、社会を分断してしまう一つの要因になったんじゃないかなと思います。 いろんなそういうデマがあったとしても、正直あちこちから出てくるわけですよね。 1か所だけから出てくるのであれば、それに対して「違うんですよ」ということで、そこに対して押さえ込むというか、ちゃんとした意見を言うっていうのはできるかもしれませんけど、正直言っていろんなとこから出てきて、それらに対して対処するっていうのは正直できないところでもあるんですね。なので、あくまでもこちら側はこういうエビデンスがあってこういうものなんだと。確かにこういう副反応はあるけど、それはもう割合からしたら、例えば10万人に1人だとかそういうレベルなので、それを無視していいとは言わないけれど、あくまでも、大きくみんなが被害を受けるようなものではないと。 最初の頃はどうしても流行がかなり厳しくて、重症化する方も多くて、そういう時期が、ワクチンが、接種が広がっていくと、かなりそれに伴って減ったんですよね。「あ、これはワクチンの効果は確かに出てるな」と。「あれだけ重症者が出ていたのがだいぶ減ったな」というのもあったので、だから私たちはワクチンの効果を実感していたんです。 その一方で、やっぱりワクチンを打ってアナフィラキシーになった例もありますので、ちゃんと注意しながら打たなきゃいけないなっていうのもあったんですよね。だけど、それはもちろんワクチンのメリット、デメリットとしてあったわけですけど、思ってもみないような、いろんな「そんなのないでしょ?」というデマが広がってしまったという部分に関しては、正直どこから出てるのかもわからないし。 これに対して具体的な対策はもう取れないなということがありましたね。 特に感じたのは、もちろんこれまでもワクチンで、例えば “失敗例”っていうのもあるわけですよね。副反応が強すぎて、このワクチンは実際開発は止まった、というのもあるし、ワクチンに対して懐疑的な見方をしてる人もいたんですけど、ここまでですね、このコロナのワクチンが始まって、ワクチンに対して敵視される強さ、その、何て言うんでしょうかね、反対運動と言いますか、そういったものがこれまで以上に強くなったというような感じはしますね。 おそらくやっぱり大事なのは、ちゃんと得られたデータをわかりやすく説明するということなんだろうと思うんですよね。単なる論文を見れば、私たちはこういうものなんだなというのはわかるんですけれども、ただそれは一般の人たちに「この論文が出てますよ」といってもそれはわからない。 それを噛み砕いて、結局は「このワクチンの有効性 これぐらいです」「副反応 こういうものがあります」「なので、これをちゃんと見比べて、それぞれの判断でやっぱり打った方がいい人、打たなくてもいい人、というのはこういう人たちなので、打った方がいいという人たちに関しては、なるべく受けてください」というのを打ち出すと。なるべくわかりやすい情報としてやるべきだし、「誰しもがみなさん打ちましょう」という発言というか、考え方は、ちょっともう社会としては受け入れられないんだろうなとは思います。 最終的にですね、やっぱりワクチンを受けるか受けないか、接種するかどうかっていうのはご本人の判断ですよということで、こちら側が提供できるのは、ちゃんとした科学的根拠に基づく情報ということで、それをどう判断していただくかということだろうとは思います。 新型コロナウイルス感染症の流行というのは、だいたい年に2回、ずっと今まで起こってきました。そしてその流行のたびに、どうしても医療機関側は入院患者も増えるんです。そしてその多くはやっぱり高齢者の方々です。そして中にはやっぱりもちろん亡くなる方もおられます。そういう中で、5類になって、社会の受け止め方としては「もうあんまり気にしなくていいんじゃないか」というふうに、社会全体がそういう雰囲気に、コロナに対して見方がだいぶ変わってきましたけど、病院の方で診ているコロナ患者さんというのは、やはり重症の患者さんを診ていると、やっぱりいるのはいます。そういう人たちが出てこないためには、やっぱり基本的にはまずは予防が大事だということで、ワクチンに関しては重症化予防というエビデンスはありますので、それについては日本感染症学会をはじめ複数の学会で、やっぱりこの次のワクチン接種についても、特に重症化しやすい方、高齢者の方に関しては積極的にワクチンを打ってくださいということが学会としての考え方になります。 ただ、もちろんそれより若い人たちだとか、お子さんだとか、そういう人たちに関しては、それぞれの判断ということが重視されますけど、全体としてとらえればですね、どうしても高齢者の方たち、何らかの基礎疾患がある方は、今のこのタイミングでもやっぱり重症化される人はいますので、そういう意味ではワクチンが「もういいですよ」とは言わない。「そういう人たちは打ってほしい」というのが学会としての考え方です。
Clip.07クラスター対策の効果・意義とは?
最初、どうしても「0」だったところに、1人、2人、3人とずっと感染者が出てきて、そういう人たちに対する関心が非常に高まって。ただ、もちろんクラスター対策、すなわち感染者を隔離してそこから広げないというやり方は、最初の段階では非常に有効なんですよね。 感染を広げないという意味では。なので、そこのクラスター対策といいますか、感染者を見つけ出して、そこの部分にちゃんとしっかり手当てをしていく、ほかに広げないようにするという対策は有効だったとは思います。 ただこれは一定程度数が少ないときの話であって、1日に日本の中で100人、200人ぐらいまでは何とかいけるかもしれませんけれど、これが例えば1万人だとかいうレベルの感染規模になりますと、とてもとてもそんな個別の対応というのはできませんので、 そうすると別の、社会全体としてなるべく感染を抑える方向の対策をとらざるを得ないと。なので、例えば「ユニバーサル・マスキング」と言って、皆さんマスクしましょうというのは、結局は、誰が感染しているかもわからない、そういう状況の中で、対策としたら、そういうことになりますよ、になるわけですが、最初のころは別に「皆さんマスクしましょう」じゃなかったんですよね。 別にそんなにリスクないし、一部のところでリスクがあるだけ。その場合はクラスター対策。でも、規模がどんどん広がっていくと、それは取る対応を変えざるを得ないということだったと思います。 なので、パンデミックもステージというのはやっぱりあるんですよね。ある程度全世界に広がっているレベルもあれば、最初は一部の地域から多発的に出てきていて、それでだんだん、例えば日本の中でも、最初の感染者から始まって、その後、数がどんどん出てくるところまでステージがあります。 そうするとその時点、その時点で取るべき対応というのは違うんですよね。そうなったときに、最初の感染者が出た後でぽつぽつ出始めたときにクラスター対策をとるとしても、ちょっと過剰な反応が起こってしまって、「この感染者はここにいて、どの電車に乗って、どこで食事をしてとか」ということがどんどん公開されていったり、あるいは「この感染者はどこどこ病院に入院しています」という、ただ単に病院の中で診ているだけなのに、その病院に近づくこと自体が怖いというような雰囲気を作り出してしまうと。そうすると、確かに「感染したくない」っていうのはわかるわけですけれども、それが過剰な反応を引き起こしてしまって、クラスター対策も結局「この地域で出たみたいよ」「どこで出たみたいよ」というのが今度過剰な反応になって、「そこには近寄らない」とか、「そこに関わった人はもう会社から辞めてもらう」とか、何か極端な反応がやっぱり起こり得るわけですよね。 ちゃんとそこにいわゆるクラスター対策班が入って、ちゃんと調べて、「ある程度、ここはこうしてくださいね」というのを現地で対応すれば、それはそれだけでも有効だと思うんですね。ところが、それを「どこどこの町のどこどこで発生しました」 で、それ以上のいろいろなインパクトがあるようなニュースがぼんぼん出ていくと、そこの受け止め方は非常に過剰になっちゃうわけですよね。だから、ある意味、ちょっとこう恐怖感をみんなが募らせてしまうと、過剰な反応につながってしまうというところはあるので、そこはある程度意識しながら情報を広げていくということかなと思います。 例えば今の時点でも、日本、例えば「麻しん」の患者さんですね、「はしか」の患者さんが一人出ると、例えば「新幹線で、何日の何号車に乗ってました」みたいなことが出てくるんですね。だけど正直言って大抵の人は『そんなのを見たって自分が乗ってたかどうかわからないよ。 確かにその日新幹線に乗ったけど』みたいな人もいるわけですよ。ということは、その情報がどこまで本来の意味の感染を封じ込める対策になっているかというと、あんまり意味はないと。ただし、何月何日にどのコンサートホールで皆さん見た人おられたら言ってくださいとか、そこら辺はですね、ある程度そこでの感染のいわゆるリスクがあるという人たちは絞れるんでしょうけど、あまり感染対策に直接的には有効じゃないんだけど、逆にむしろみんなの何か インパクトだけ強いような情報が出てくると、それはあんまり意味がないといいますか、伝え方にもよるのかもしれないですね。
Clip.08次のパンデミックにどう備えるのか?
最初の頃、コロナの混乱が起こって、そしてその後ワクチンが開発されたり薬が開発されたりした中で、例えば国としてはですね、ワクチンの開発が遅れたという反省のもとに、内閣府の会議がありましたけれれど、今後の新たな感染症に対してどう取り組むか、ということで、やっぱり今回のものを反省点として次につなげるためにっていう対応は今とられようとしているわけですね。 そういう意味では、何が原因で諸外国のワクチン開発に比べて日本は遅れちゃったのかとか、あるいは、対策として今後やるべきことは何なのかとか、いうことは話し合われています。 そういう意味では国の方針として、次のパンデミックに備えようということは進められてはいるんですね。 ただそれはそれとして、そこに例えば学会だとか、いろんな団体だとか自治体だとか、そういう関係するようなところが、もうちょっといろんな意味で「今後どうやっていきましょうか」っていうことは、正直言って今はある意味ちょっとトーンダウンしている感じがいたします。 それは “のど元過ぎれば熱さを忘れて” もちろん今後「明らかに来年 こういうのが来るよ」って言われれば、それは私たちはそれに対して備えていくと思いますけど、いつ来るかわからないものにどこまで頑張ってやっていこうかっていう感じは、それは理解できるわけですよね。 ただし、やらなきゃいけないことであることは間違いない。そうすると、どうしても定期的に話し合いを続けていったりとかといういうことは大事ですし、やっぱり今やるべきことは、一つは、もう一回振り返って、私たちがやったことの問題点とか、ある意味及第点もいいんですけど、ちゃんと反省して評価して、「次にやるべきことは何なのか」っていうのをもう一回見直しておかないと、評価しておかないといけないのかなと思います。 そうしないと、結局次来た時にどうあるべきかはやっぱりわからないので、「もう済んだことだからいいんじゃないか」とかいうことじゃなくて、「私たちはあの時にこうやったけど、それは本当に正しかったのかどうか」ということをもう一回評価して、その上で、「次にどういうことをしましょう」ということで次に取り組んでいくということが大事だとは思います。
Clip.09感染症専門医という存在・いざというときに備えるために
もちろん、感染症の専門医だからといって、全く未知の感染症にすぐ対応できるわけじゃないんですね。ただそうはいってもそれなりの知識がある人が病院の中にいて、どうしても患者を受け入れなきゃいけなくなったときは、その人をリーダーとしてしっかり病院の対応をまとめる役割を担っていただけると思います。 ただその数が、日本の中では専門医を取っている方が2000名ちょっとぐらいですので、そうすると少なくとも「1病院に1人」なんていうレベルじゃなくて、それなりの規模の病院なのに「うちには専門医がいません」という病院がたくさんあります。 そういう中で、でも感染症の患者がいままでにないものが出てきました、そこで診てくださいと言われても、「いや、うちはそんな対応できませんよ」ってことになっちゃうんですね。そういう意味では、もっと感染症専門医を増やして、多くの病院に配置するということが本来のあり方だとは思います。 ただし、それを妨げるものはいろいろ要因としてはあります。少なくとも、例えば感染症の専門医が、多くの先生たち、医師の先生たちが目指すような領域になってるかというと、そこまではないんですよ。感染症の領域は特殊です。例えば、循環器だとか消化器だとかですね。そういった他の領域に比べて患者はそんなに多いわけじゃないんです。そうすると、例えば感染症の専門医としてやった時に、専門医っていうか、感染症の診療科としてやった時に、医療機関でも、患者さんをどんどん診て収益を上げてとかというような診療科にはあんまりならないんですね。ただ、病院全体の感染対策をやるとか、あるいは感染症に関してのコンサルテーションをやるとかいう意味では非常に重要な役割を担っているんですけど、あんまりどんどん収益を上げるような診療科ではない。そうすると、どこもそんなに積極的に感染症専門医を雇いたいですっていうような状況ではないんです。ましてやいま、医療機関はかなり収益が下がっていますので。そういう感染症専門医を置くというのは病院の中で重要な位置づけだからということで置いていますけど、収益を目的として置いているとはあんまり思えない。そういう中で、私は感染症の専門医になりたいですっていう人もそんなには多くないんですね。 だからそこを、「いやいやもっと社会としてのニーズがあるんだよ」と。「そういう領域も面白いんだよ」ということで、学会としてはもっと増やそうということで取り組んではいます。なので、それが本当にうまくいけばもっと増やせはしますけど、ただ、そんなに数年で増えるものではありません。10年、20年かけてもっと増やしていくものですから、これも取り組みを続けていきたいと思います。 ただそうなると、「たとえば来年、もしパンデミックが起こったらどうするの?」ということを考えると、いまいる感染症の専門医を急激には増やせません。 となると、今の役割をもうちょっと変えて、例えばお一人の先生が複数の病院の、ある程度対応といいますか、相談を受けられるようにするとか、地域の中でのネットワークを作って相談ができるような形のものを作り上げるとか、ということで、効率的に感染対策に役立てられるような専門医のあり方っていうのも考えていかないといけないし、なかなか非常に“土壌”っていう意味では、まだどんどん感染症の専門医が出てくるような状況じゃないので、いまいる専門医の人たちをもっと活用していただけるようなやり方に変えていかなきゃいけないんだろうとは思います。 今回のことがあって、そこのエリアの中で感染症の意見を言っていただける方、指導していただける方というのを、たとえば保健所、自治体がある程度ちゃんと選んで、そこの指導者としての役割を担っていただくようなところはあったりはするんですよ。 そうなると、逆に大変は大変なんですね。実はある病院でクラスターがが起こってます。そこに行って指導してくださいと言われるんですけれど「いやもう自分の今の病院の中の対応だけで手一杯なんだよ。それでそっち側に行けというのか」みたいな感じで、結構その辺は「いくらなんでも全部は無理でしょう」ということで、ちょっと負荷がさらに大きくなったりする部分はあります。 ただそれを例えば、そうはいっても、例えばネット上で結んでみんなで話し合いをして、その時に指導するようなことはできるんですよね。なので、現場での指導をどこでもやってくださいって言われると確かに大変ではありますけど、やり方によってはそういう地域の指導的な役割を担っている先生が非常に活躍しているような地域もあります。 医療従事者の中で医者だけが感染対策に携わってるわけじゃないので、実は看護師の中にも「感染管理認定看護師」っていう役割を持った、ちゃんと承認された立場があるんですね。それが非常に重要な役割を別に担っていて、例えば極端な話、さっきのクラスターへの指導っていうのも、そういう資格を持った看護師は知識も豊富です。ちゃんと指導ができるんですね。「ここはこうしてください」とかいうことで、感染症の専門医として、その感染している人の診療という面では非常にその役割は重要なんですけど、感染対策面での指導だったら非常に看護師で優秀な人たちもたくさんいますので、そういう人たちも一緒になって、いわゆる感染対策面の対応もやってるということになります。
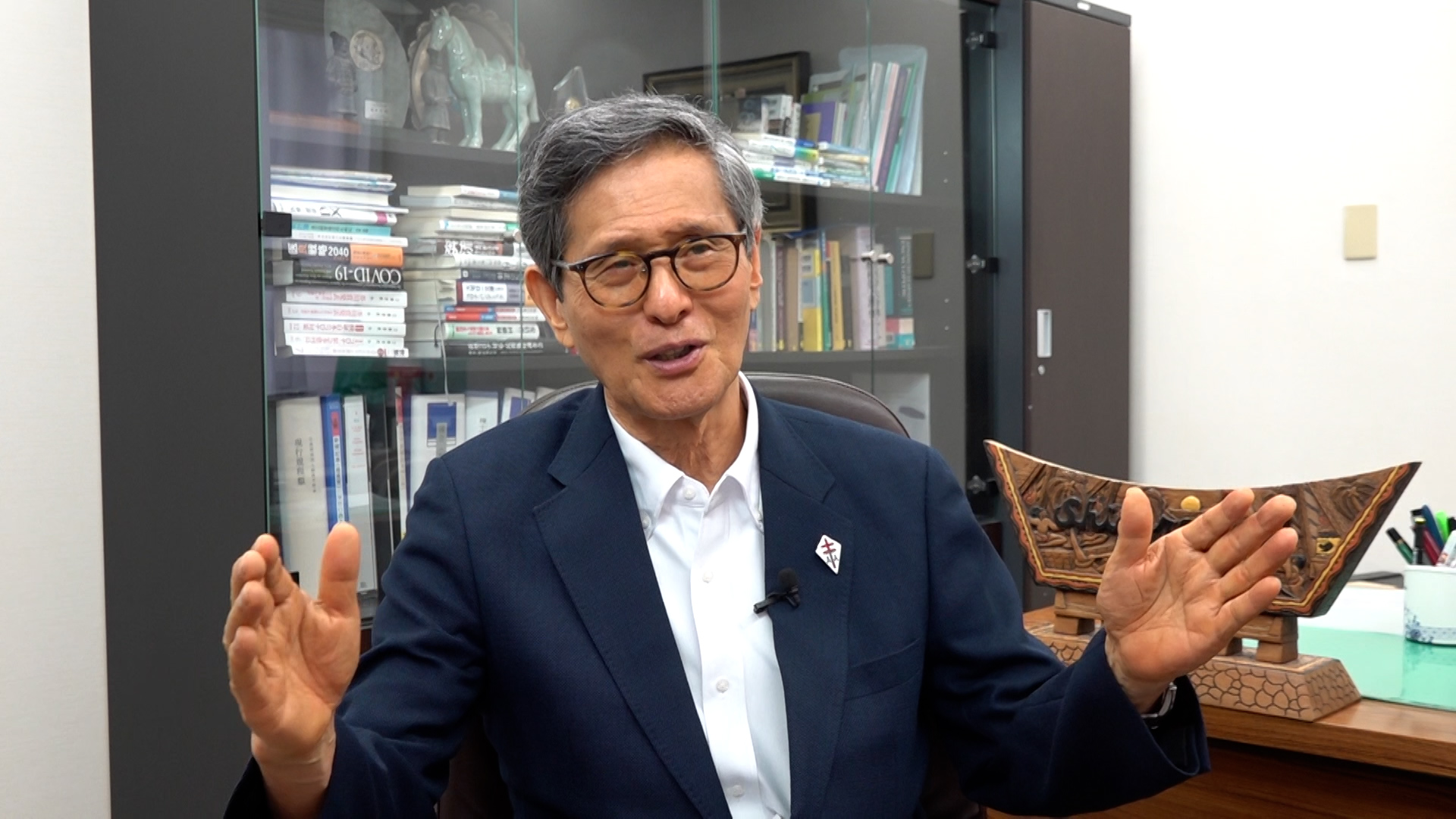
- 新型コロナウイルス感染症対策分科会 元会長
- 公益財団法人結核予防会 理事長

- 沖縄県立中部病院
- 感染症内科・地域ケア科 副部長
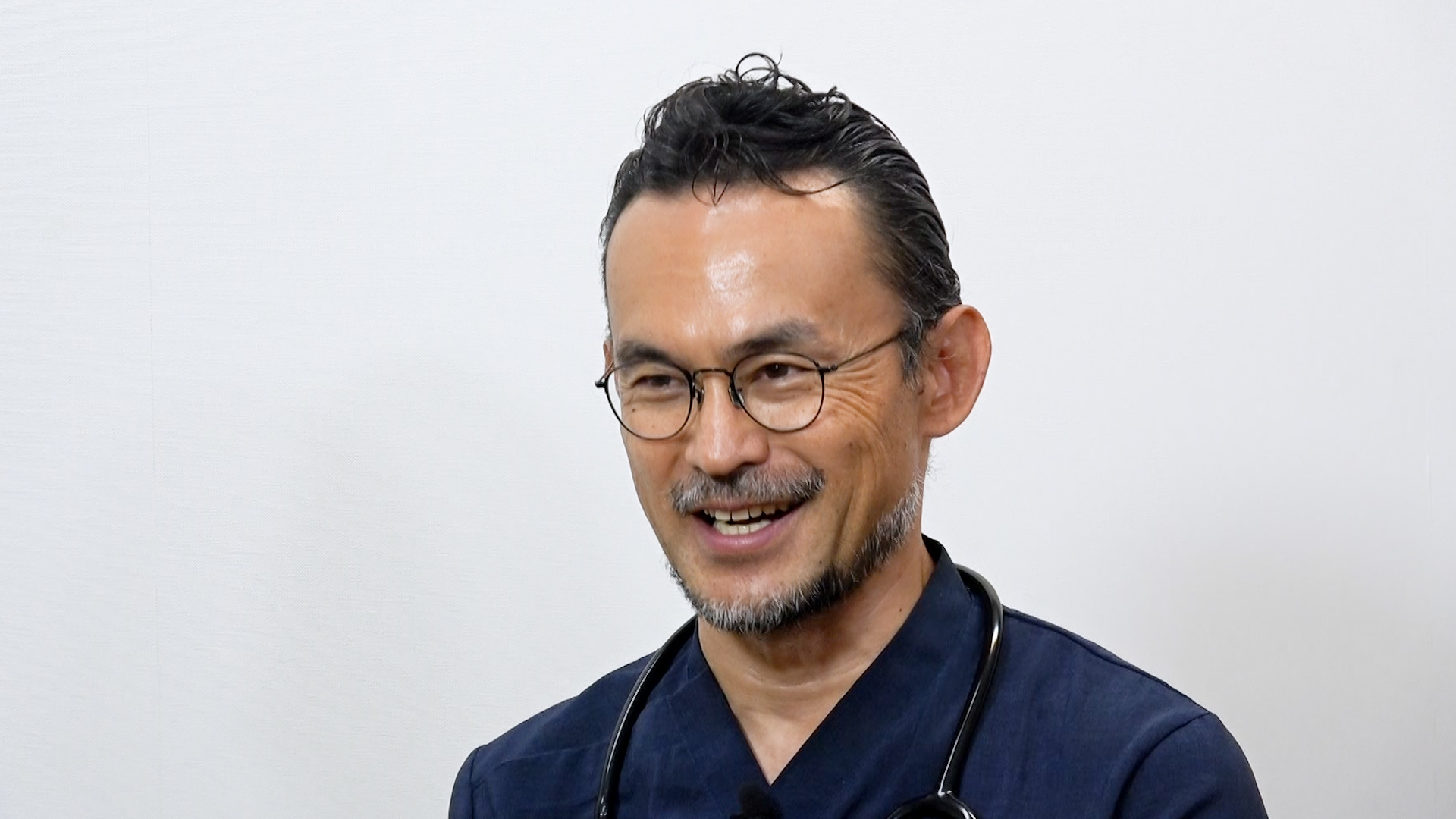
- 医療法人社団 悠翔会 理事長
- 訪問診療医
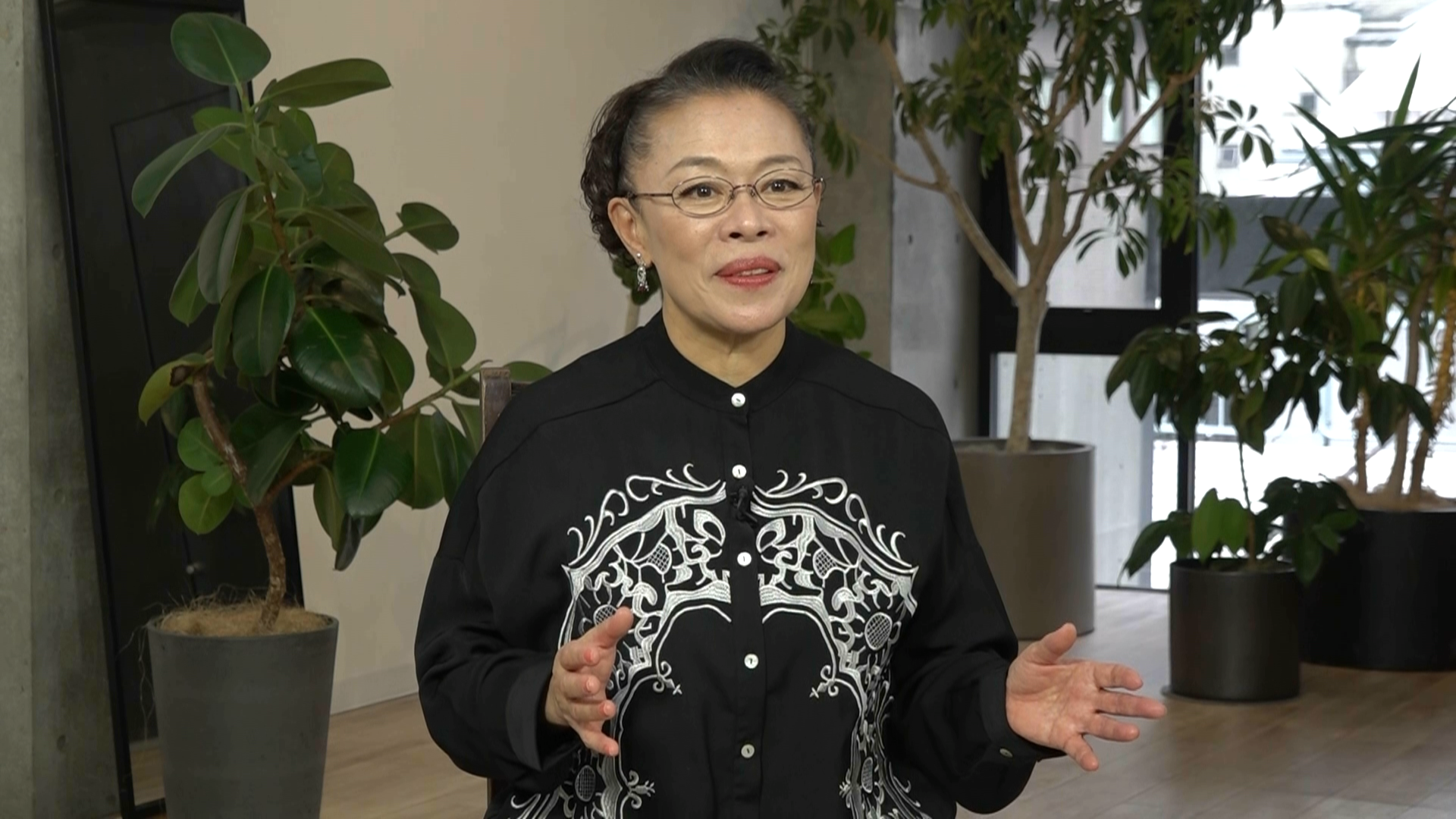
- 俳優・タレント
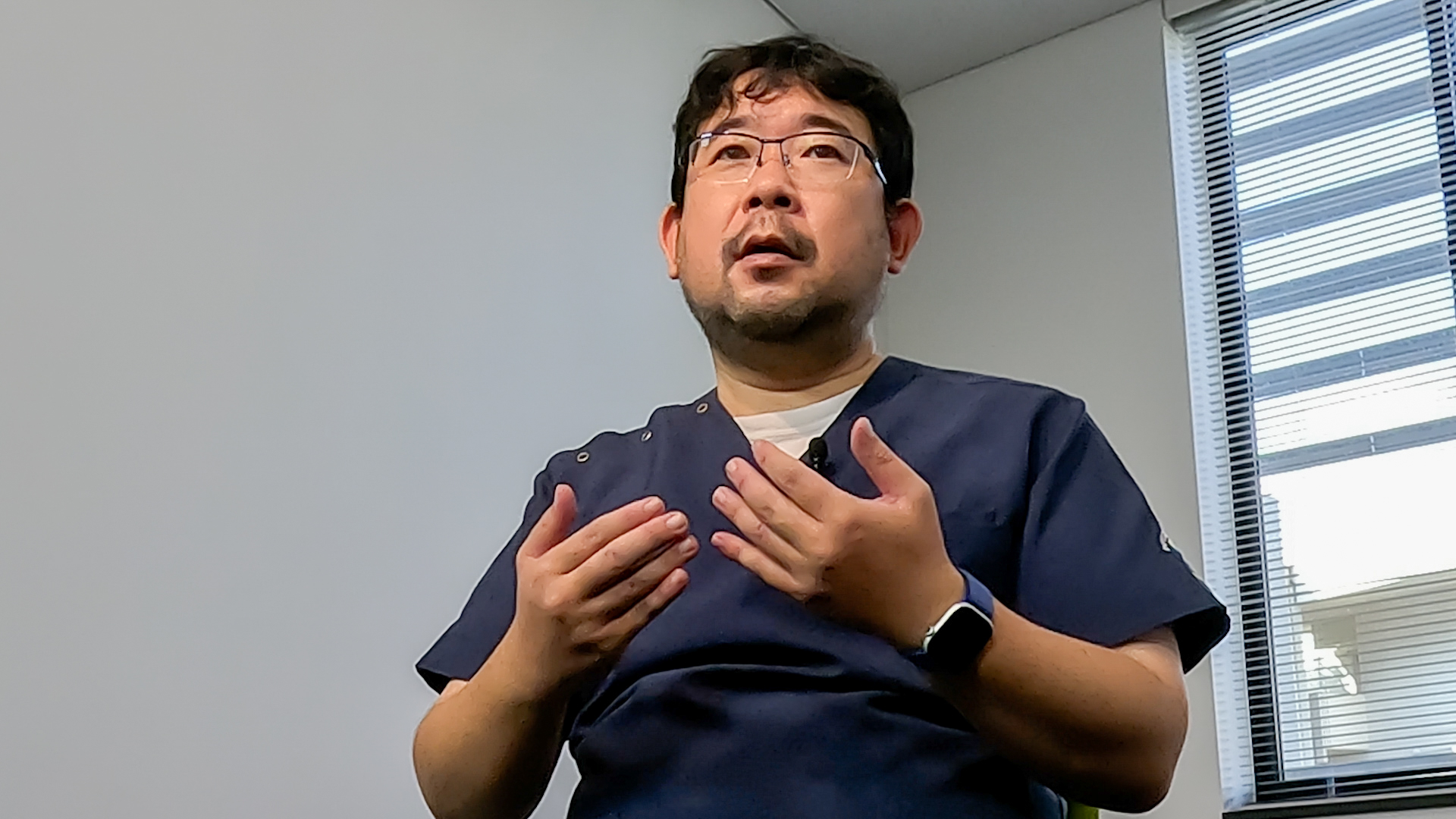
- 大阪大学医学部附属病院 感染症内科 診療科長
- 大阪大学大学院医学系研究科感染制御医学講座(感染制御学)教授
