新型コロナウイルスへの提言
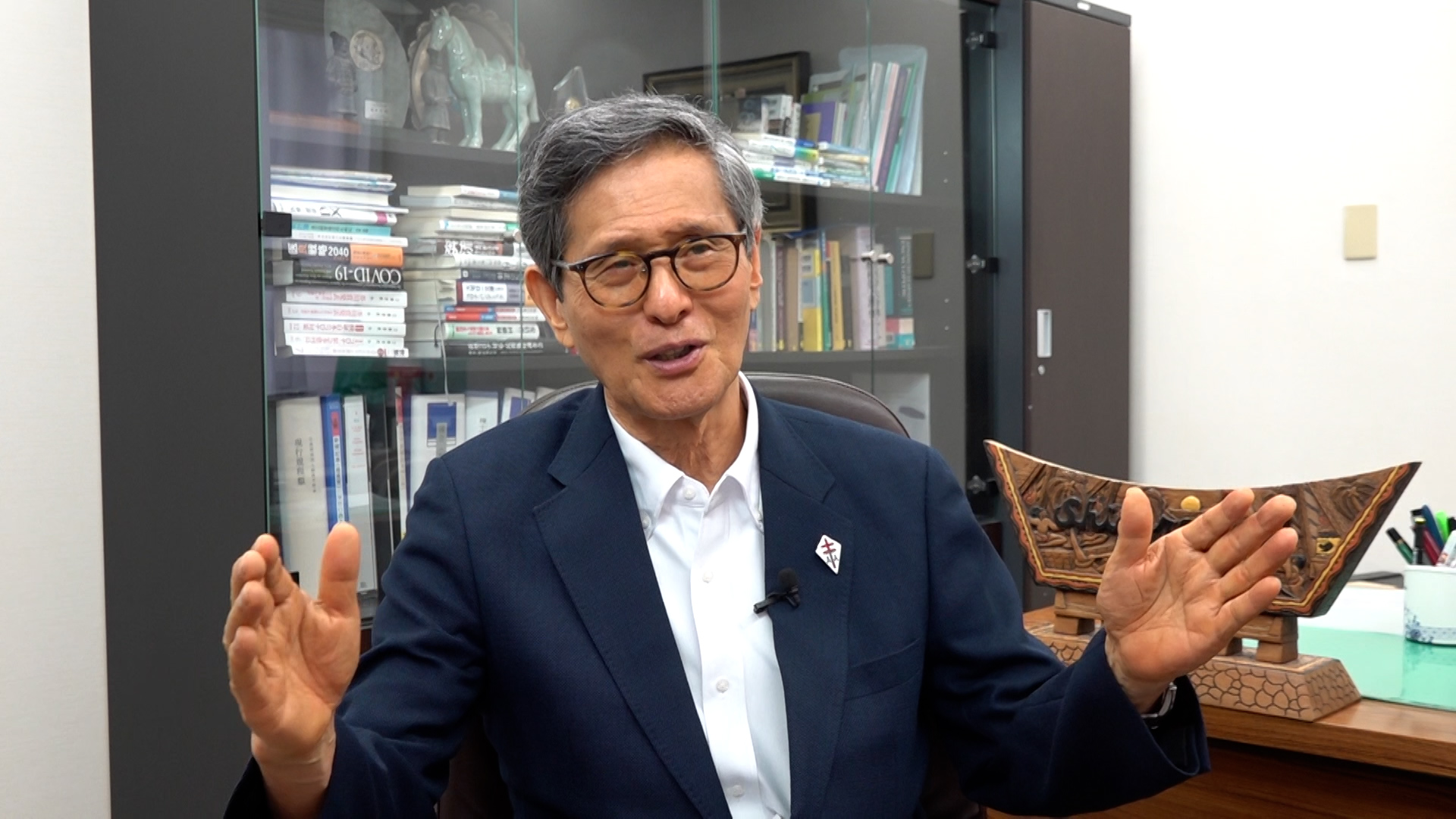
世界を震撼させた新型コロナウイルス。日本の対策は、どのような理由で行われたのか。そしてその結果は?▽対策の最前線に立った尾身茂さんに聞く。 緊急事態宣言を実施した理由は医療崩壊の危機▽緊急事態宣言の結果、感染対策と経済の両立はできたのか?▽ワクチンの効果と副反応の事実▽人々が不安をもつ訳は?▽オリンピック無観客開催の舞台裏▽コロナパンデミックは今も続いている。求められる対策は?▽コロナ最前線を経て、次のパンデミックのために必要な備えは?コロナ5年を検証するロングインタビュー。
ProfileView More
1978年自治医科大学卒(一期生)。卒業後、東京都立墨東病院研修医、伊豆七島勤務医等。1990年よりWHO西太平洋地域事務局に勤務。西太平洋地域において小児麻痺(ポリオ)の根絶対策などで陣頭指揮。1999年WHO西太平洋地域事務局長就任後、SARSの制圧及び各加盟国の地域医療対策や結核対策等で陣頭指揮。2009年よりWHO執行理事。2012年より独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(RFO)理事長、内閣官房新型インフルエンザ等対策有識者会議の長。2014年4月から2022年3月、独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)理事長。また、社会貢献活動として組織の利害やイデオロギーにとらわれず、将来の社会づくりに貢献すべく2015年9月、NPO法人「全世代」を設立。2020年2月、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 副座長、2020年7月、新型インフルエンザ等対策有識者会議 新型コロナウイルス感染症対策分科会 会長。2021年4月、新型インフルエンザ等対策推進会議 議長、新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処方針分科会 分科会長、新型インフルエンザ等対策推進会議 新型コロナウイルス感染症対策分科会 分科会長就任。2022年4月より公益財団法人結核予防会 代表理事、独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)名誉理事長。2022年6月より公益財団法人結核予防会 理事長 現職。
Profile
1978年自治医科大学卒(一期生)。卒業後、東京都立墨東病院研修医、伊豆七島勤務医等。1990年よりWHO西太平洋地域事務局に勤務。西太平洋地域において小児麻痺(ポリオ)の根絶対策などで陣頭指揮。1999年WHO西太平洋地域事務局長就任後、SARSの制圧及び各加盟国の地域医療対策や結核対策等で陣頭指揮。2009年よりWHO執行理事。2012年より独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(RFO)理事長、内閣官房新型インフルエンザ等対策有識者会議の長。2014年4月から2022年3月、独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)理事長。また、社会貢献活動として組織の利害やイデオロギーにとらわれず、将来の社会づくりに貢献すべく2015年9月、NPO法人「全世代」を設立。2020年2月、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 副座長、2020年7月、新型インフルエンザ等対策有識者会議 新型コロナウイルス感染症対策分科会 会長。2021年4月、新型インフルエンザ等対策推進会議 議長、新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処方針分科会 分科会長、新型インフルエンザ等対策推進会議 新型コロナウイルス感染症対策分科会 分科会長就任。2022年4月より公益財団法人結核予防会 代表理事、独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)名誉理事長。2022年6月より公益財団法人結核予防会 理事長 現職。
Clip.01政府・専門家によるパンデミック対策の目標と結果
○緊急事態宣言の目的 今回のコロナ対策の目標を大きく分ければ3つあったと思います。 1つは感染者を0にすることは、これは絶対無理なので、なるべく重症者、死亡者を少なくするということは非常に重要な目標。それから、感染対策を行う中でも、社会経済の影響をなるべく最小限にしたいという思いがありました。その中で、例えば緊急事態宣言など強い対策を打つ際は、何を目印にしたかというと、医療のひっ迫。医療のひっ迫だけはなんとか抑えたいということで、この1と2に加えて、医療のひっ迫を何とか抑えるというのは大きな1つの目標でした。 ○新型コロナウイルス 各国の累計死亡者数 これは死亡者の推移。いくつかの国の代表的なもので、右の方を見てくれば、アメリカ、イギリス、それからちょっと下、ドイツ、カナダ、それから韓国、日本となっていますけれども、ヨーロッパの死亡者の数の増加はかなり急激ですよね。これにひきかえ、日本の場合はもう最後までそうなんですけれども、特に初期におけるこの差は、欧米先進諸国と日本ではかなり違う。これは一つの特徴。 これは一番左がアメリカ、それから次がイギリスで、一番右がシンガポール、ニュージーランド、日本、日本は右から3番目ですけれども、初年度、2020年赤、その次が緑、その次が3年目が黄色になっていますけれども、これを見ると、ヨーロッパ、OECDの国は最初の年あるいは2年度にかなりの死亡者が出たということで、一方日本の場合、右から3番目ですけれども、1年、2年度はかなり抑えて、3年度は実は日本の超高齢化社会を反映して、亡くなった多くの人が高齢者で、もともと介護の必要があるような人が感染をすることによって体力が落ちていくという人も結構いたということが、これがファクトですね。 ○GDPの落ち込み 3年間のGDPの落ち込み、3年間の平均は欧米先進諸国並みということが研究者、経済の専門家の間でのコンセンサスになっております。 理想的には、死亡者も圧倒的に少ない、経済へのGDPの影響も圧倒的に少ないというのが理想的ですけれども、経済の落ち込みについては欧米先進諸国並み、これをどう評価するかはいろいろな意見があると思いますが、これが、ファクトです。 全体的な私の感想は、死亡者の人口当たりが少なかった。また、GDPの影響は欧米先進諸国並みで特に悪かったわけではないということは、ある程度、よいことだったと思います。しかし同時に課題もあったということも確かです。さっき示した死亡者とかGDPの客観的なデータの裏には、さまざまな次のパンデミックに備えての課題も見えてきた。よかったことと課題が両方見えた、というのが私の個人的な見解です。 ○一定の効果をもたらした要因は? 大きく分けて4つあったと思います。 緊急事態宣言を出す前の初期の対応というのは日本はかなりしっかりやったと思います。例えばクラスター対策、あるいは保健所による積極的な疫学調査などの対応をかなり早いうちにしっかりやったというのが1つ目。 ワクチンが出てきてからワクチンをかなり広範に投与された、あるいは治療薬も完璧ではないけど出てきた、そういう医療関係者、自治体などの努力というのは、これは間違いなくあったと思います。 それから、海外ではロックダウンという強い法的措置のある対策をとったわけです。日本は要請ベースですよね。協力しないからといって罰金を取ることはなくて、自主的な協力を人々に任せていたわけです。かなり多くの人が協力してくれたということは間違いなかったと思います。 それから、ハンマー&ダンスといって、医療のひっ迫が起こりそうになると、強い対策をとって、例えば緊急事態宣言。医療のひっ迫が軽減すると、そういう対策を解除する、このハンマー&ダンスを4回か5回繰り返した。ずっと強い対策を続けたのではなくて、医療のひっ迫の状況に応じて対策の強度を調整してきた。この大きく分けて4つぐらいがあったのではないかと私は考えております。
Clip.02ワクチンの効果は?世界のデータを紐解く
○ワクチンの効果について ワクチンの効果については、さまざまな意見がある。私は、そのことは健全なことだと思います。ワクチンの効果を評価、議論する際には、さまざまな考え方があることは私は当然だと思いますけれども、基本的なデータ、ファクトについては共有した上でいろいろな議論がされることが重要だと思います。 ○新型コロナ 感染者数と死亡者数 おそらく多くの方がちょっと驚くかもしれませんけれども、このグラフは左の方から第1波、右の方の6、7、8という波で、青が感染者数を示しています。赤が死亡者の数を示していますけれども、皆さんパンデミックの途中から、感染してどのぐらいの人が亡くなるのかという致死率というものが減ってきたから、途中から普通の病気というふうに考えてもいいのではないかという意見がありましたよね。確かに致死率というものは特にオミクロン株になり、かなり減ってきたのです。 しかし、これを見ていただくとわかりますが、死亡者の絶対数は、1波から8波にくると、どんどん増えているんです。このことは多分中にはご存じない方もおられる。なぜ致死率が低くなっているにもかかわらず死亡者の絶対数が増えたのかというと、致死率の低下を補って余りあるほどの「感染伝播力」が強かったということです。例えば、致死率が10分の1になっても、感染伝播力が200倍になれば、20倍の死亡者が出るということになりますよね。そういうことが今回起こったということであります。このことをまず踏まえた上での議論が必要だと思います。 ○ワクチンの効果「重症化・死亡予防効果」 このワクチンの効果については、パンデミックの初期にはかなり強い期待があったんです。下の方はワクチンを打ってから100日ぐらいたつと、これぐらいの差が出て、ワクチン効果が極めて強くて、95%以上の予防効果があったというのが当初出されて、多くの人が期待した。 実際にこれは世界で初めてワクチンを投与したイスラエルのグラフで、右の方に3つ、縦の矢印がありますけれども、ワクチンを打とうとすると、どんどん感染者が減ってきて。当時、これの重症化予防効果、発症感染予防効果、両方高くて、ワクチンを接種すれば制圧、収束にいけるというようなことを示すデータですね。そういう期待が初期にあった。 次にはっきりしていることは、重症化予防効果というのは発症予防効果に比べて、より高かった、効果的であった。したがって多くの死亡が回避されたと考えられています。 ○新型コロナ ワクチンのエビデンス 上のふたつ、色がついているのが死亡だとか入院の予防、重症予防効果ですね。これを見ると特に重症予防効果はかなり長く続く。だけど、感染予防効果はだんだんと減ってきて、最後になるとかなり減るという、この2つは明らかに差があったということですね。効果を完璧に判定することはなかなか難しくて、研究には一定程度の限界がありますけど、ここが一つのポイントで、分析方法が異なる国内外の研究により、「重症化予防、死亡予防効果」があるということが指摘されていて、これらが信頼されている医学雑誌などで公表、掲載されているということです。 研究のいくつかの例だけを示すと、まずは国内の研究ですけどVERSUS Study、これはいわゆる症例対照研究といって、比較的正確な結果が得られる方法です。それによると重症化予防効果、60歳以上が45%、それから国立感染症センターとか3つの大学などがやった研究、これは二項分布を用いた数理モデルという、また別の方法でやった研究ですけど、それによると、ここに60、70、80、90歳以上でそれぞれ88、83、83、77と高い有効性が示されている。 海外でもこれはEuro Surveill.(ユーロサーベイランス)といってヨーロッパの研究ですけど、スクリーニング法というのを用いて、やはり60歳以上は効果が71%、それからJAMAというしっかりした雑誌に書かれていて、これは症例対照研究というので、18歳以上における入院予防効果62%。もう一つは他施設共同症例対照研究でアメリカのMMWRという、これも信頼された雑誌に、65歳以上の入院予防効果がある、接種後7から59日で54%、接種後60から119日で50%あったというような異なる方法で同じような結果が出ているということだと思います。 ○発症予防効果 発症予防効果については、変異株の出現によって時間経過とともに変化したんです。 ○ワクチン有効性の減弱 このグラフですけど、上の赤の方はそれまでの株で、この下の青い点線がデルタ株です。これを見ると最初のころは、結構高い感染予防効果があるけど、だんだんと下がってくることがわかります。 つまり、デルタ株流行期初期には発症予防は短期間であったけれども、一定程度認められた時期があるのです。しかし、時間の経過とともに減弱したということです。 これはイギリスで発表されたデータです。オミクロン株の流行期になると、当初は60%ぐらいの発症予防効果があったんだけど、6か月後には30%に減ってしまう。もちろんこれはブースター接種により一定期間回復します。国内でも、長崎大学を中心にされた国内多施設共同症例対照研究ということで、これは世界的に認められたTest-Negative Design(テストネガティブデザイン)というWHOからも推奨されている方法で、その結果デルタ株では2回接種後の有効性が88.7%、オミクロン株では42.8%まで感染予防効果というのは減ってくるということが国内でも認められたということです。 感染予防効果も初期にはありましたが、だんだんと時間とともに少なくなって、ワクチンを打っても感染した人、あるいは1度感染しても2度かかる、つまり、感染防止効果は完璧ではなくて限界があったということです。しかし、一方で、重症化と死亡予防効果はかなりあったというのが、国内外のさまざまな異なる研究によって指摘されています。
Clip.03ワクチンの副反応は? 科学的検証と人道的な対策
○ワクチンの副反応について 副反応を評価する仕組みとして日本には実は目的の異なる2つの制度があります。そのことが必ずしも一般に共有されていない可能性があるので、少し説明をしますと、 2つの異なる制度のうち、一つは「予防接種後の副反応疑い報告制度」と呼ばれているもので、これはワクチン接種後に発生するいろいろな不具合がありますよね。ワクチンを接種した後に残念ながら亡くなることもあるわけです。その死亡がワクチン接種と因果関係があるかないかを調べる制度です。これが一つの制度、これは厳密に科学的にやる制度です。 それからもう一つ、別の考えで行っている制度が「健康被害救済制度」というもので、これは厳密な因果関係が証明できなくても、つまり因果関係があるかないかわからなくても、ワクチン接種後に発生した健康被害、死亡に対して、これは人道主義的というか、そういう意味でなるべく広範囲に給付をして救済をするという目的の制度です。 ○新型コロナウイルス接種後の死亡報告 これが最初の方です。厳密に因果関係があったかどうかを調べる。そこに報告に上がってきたのが、これは特に医療機関なんかを中心に上がってきますけども、2294例が対象になった。その中でワクチンと因果関係が否定できない、つまりあるかもしれないと言われたのがたった2例で、因果関係が認められないというのも11例ありましたけど、2294例のほとんど2281例は情報不足などによりワクチンとの因果関係が評価できないというのがこの報告制度の結果です。これをどう考えるかというのは後で話しますがこれがファクトです。 2つ目のスライドは、なるべくはっきり因果関係はなくても救済しようという国の考えでできたもので、1805例がその対象になりましたが、そのうち1032認定されて給付を受けて、否認されたのは650例、それからまだ確認中というのが123例です。 因果関係が否定できないとされた2例と、認定された1032例、この2つの数字の意味するところは、今申し上げたように異なるわけです。 このことをしっかりと認識した上で議論をした方がいいと思います。 ○ワクチン副反応 これから求められること 今のままでいいのかというと、この第1番目の報告制度でほとんどが判定できないということになっているわけです。これはなかなか一般の人々の感覚とすると、もう少し判定できないのかというふうになりますよね。ただ、今の報告制度ではどうしても情報が不十分で判断できないというのは、これがファクトです。 したがって、私はこれから政府にやっていただきたいと思うことは、より精細で正確なワクチン接種歴、これが必ずしも十分ではないです、及び医療データもちゃんと収集することが求められますよね。この2つを突き合わせる、突合することをしっかりやって、実際そうしたより良いシステムになったときにどう結果になったかということを、国がしっかりとわかりやすく説明するということが必要だと思います。しっかりしたデータシステムを構築する必要があると思うんですけど、国の方もその方向で進めているということなので期待をしたいと思います。
Clip.04緊急事態宣言に効果はあったのか
○緊急事態宣言に効果はあったのか 緊急事態宣言というのは東京都を中心にこの3年半に4回出している。それを出す目的はもちろん死亡者感染レベルを低くしたいということがありましたけど、医療のひっ迫、崩壊が起こってしまうと、なかなか経済と感染症の両立というのは難しくなりますよね。 したがって、緊急事態宣言を出すときの判断の基準、最も強く考慮したのは、医療のひっ迫が起こりそうになれば、これを何とか崩壊までにいくのを防ぐことが一つの緊急事態宣言を出す目的でした。そういう考えで、実はハンマー&ダンスをやってきたということです。 ○緊急事態宣言と感染状況の関係 これは東京都です。第1波から第8波まで赤が死亡者。だんだん増えてくると医療のひっ迫が起こってきます。第1回の緊急事態宣言が一番左です。右のほうに行くと第2回。緊急事態宣言を出すと人と人の接触が減るので医療のひっ迫が軽減してくる。緊急事態宣言を出すと、だんだんと死亡者とか感染者の数が減ってきているのはわかりますよね。これはファクトです。 ○緊急事態宣言の効果 どう評価すればよいのか? 緊急事態宣言の効果測定には、「実効再生産数」というものを使用することが多いです。実効再生算数とは感染の流行時、何らかの対策をしているわけですよね。全く0じゃない。一人の感染者が平均して他の人にどれだけ感染させるかの数です。 一番下に書いている基本再生産数というのは、何もしない、対策もない時の数です。実効再生算数というのが1より下回ると、感染の収束に向かうということを示す。実効再生産数が1を超えてしまうと、どんどん感染が拡大する。こういうことを前提にいろいろな研究がなされています。 感染を減少させる効果というのは、実は大きく分けて2つあるということがわかっています。1つは情報効果。これはマスコミからの医療ひっ迫が起こっているような情報などをもとに人々が自発的に接触機会を減少させることです。介入効果というのは、緊急事態宣言など、国の正式な介入によるものです。 ○行動変容の決定要因に関する分析例 このスライドの縦線は、人々がどれだけ国や自治体の要請に応えてくれたかということで、上にいけばいくほど協力の度合いが増えてきた。 横軸は時間の経過です。途中に2つの縦線がありますよね。左側の縦線は、第1回目の緊急事態宣言を出した日。右の方に行った縦線が緊急事態宣言を解除した日です。それで2つの色がありますよね。赤とブルー系、ブルー系をまず見てください。ブルー系の上昇はもうかなり左の方から始まっていますよね。 これを見ると、緊急事態宣言が出る前から人々の行動変容が起こっているのがわかりますよね。 これはなぜ起こったかというと、マスコミなどを介していろいろな情報が入ってくる。これによって人々が既に緊急事態宣言を出す前に行動変容を行ってくれた。赤は緊急事態宣言を出すことによって、さらに上乗せされたということを示すものです。これは東京大学の渡辺教授たちがかなり早い時期にまとめてくれた論文であります。 ○介入効果と情報効果の年齢別推計値 さらに詳しく見ると、右の方を見てみましょう。情報効果を見ると右の方が70歳代高齢者、左の方が20歳代。これを見ると情報効果は明らかに高齢者に効いている。一方、介入効果はどういうことかというと、高齢者はあまりいない。既に情報効果が効いているから。しかし、国が正式に緊急事態宣言を出すと、若い人も協力し始めてくれたということを示す。 赤と青は男女の差で、女性の方がより慎重だったということがわかると思います。 ○緊急事態宣言の効果 どう評価する? 緊急事態宣言の効果を評価する際のいくつか注意点があって、これは緊急事態宣言を発出する以前に、自治体独自の対策やさっきの情報効果があるために実効再生産数が緊急事態宣言が発出前に減ってくることがあるんですね。 しかし、これをもって緊急事態宣言の効果がないとは判断できないという注意点が一つあると思います。 ○東京の実効再生産数 右の方を見てください。真ん中に2つの点線がありますよね。左の方が東京都が独自の外出自粛をした時の線です。右は国の緊急事態宣言を出した時です。これを見ると何もする前は実効再生産数1.73あったんです。 ところが東京都が自粛要請をすると下がっている。さらに緊急事態宣言を出すと0.59に下がったということです。 今、緊急事態宣言の効果というものを評価しようとしているわけですが、感染状況に影響を与える要素というのはいっぱいあるわけです。緊急事態宣言以外にも、例えばマスコミなどからの情報効果、これは先ほど言いましたよね、流行している変異株の性質、アルファ株とデルタ株、どんどん変わってくる。 それから、緊急事態宣言を出していない時期でも、この3年半は常に何らかの注意喚起や感染防止の協力要請なども行われていたわけですよね。今言ったような要素が複雑に絡み合っているので、緊急事態宣言だけの効果の判定というのはなかなか厳密には難しいですよね。 しかし、そうした中でもさまざまな研究がなされていて、緊急事態宣言の効果はあったとの指摘が出されて、これらがやはり信頼できる医学雑誌に掲載されています。緊急事態宣言の効果はパンデミックの時期によって違いますから、一つずつ見ていきます。 第1回の緊急事態宣言下の実効再生産数は0.36でした。また、基本再生産数からの相対的減少は86%であったというのが一つのデータです。なお、基本再生産数というのは、先に述べたように、対策も何もしない時に一人の感染者が何人感染させるかの数です これも第1回の緊急事態宣言の効果ですけど、東京と大阪を調べると、第1波流行期、移行期、それから緊急事態宣言を出した時期と分けると、東京ではそれぞれ1.78、0.74、0.63、大阪でもだんだんと実効再生産数が緊急事態宣言を出すと減ってくるというデータも出ている。 第2回の緊急事態宣言の効果を研究したものですけど、先ほどの情報効果。上の方ですね、これはだんだんと効いてこなくなる。1回目は効いてくるけど、2回目は同じことでもだんだん慣れてくるということで、全体的に情報効果は1回に比べて減ってきました。介入効果は営業時間の短縮の要請で、21時以降の人出が減ってきて新規感染者が減ったし、それから介入効果は70歳ではあまりないんだけど、20歳代で多くなったということもわかっている。 第3回の緊急事態宣言の効果についてです。対策により実効再生産数が1より下回った都道府県の数を調べました。 ところで、重点措置というものがありましたよね。営業時間の短縮をしましたが、重点措置により、実効再生産数が1を下回ったのは、16都道府県のうちわずか6都道府県でした。一方、緊急事態宣言は10都道府県のうち、ほとんどの9都道府県で、実効再生産数が下回ったという結果も出ています。 これは第4回の緊急事態宣言、これは最後です。第5波ですけども、急速に収束してきたんです。それについていろいろな医学系の専門家だけでなくて他の専門家、厚労省の専門会議以外の専門家の人たちがやった共同の研究です。この急速な収束の要因はいくつかあって、例えば当時、緊急事態宣言が出ていたので、感染拡大時の接触機会の減少。それから、さっきの病床圧迫や不安によるリスク行動の回避、自然感染やワクチン接種による市民の間で免疫獲得者の割合の上昇、などです。 こういうことが複雑に絡んでいたが、接触機会の減少というのも一定程度関与したのではないかというのがかなり厳密なスタディの結果です
Clip.05経済と感染対策の両立
○オリンピック無観客開催について 感染症対策の専門家は経済を無視したんじゃないのかというイメージが一般にあるかもしれませんが、我々は最初の頃からの政府への提言に何度も、経済と社会、感染症の両立を目指すんだということを申し上げてきた。バランスと言ってもどこかで、どこかでどちらに軸足を置くかということが具体的には出てきますよね。それがGoToであり、オリンピックが一番わかりやすいですよね。GoToとオリンピックが基本的には2大テーマ。我々の意見と政府(の意見)。 我々(専門家は)何を考えていたかというと、経済の落ち込みはなるべく少なくしたいということで、クラスター対策やハンマー&ダンスもそうです。場合によっては、感染者の数、死亡者の数、医療ひっ迫を防ぎたいということだけであれば、緊急事態宣言をずっと出してもよかったですよね。他の国ではロックダウンを長く継続した国もあります。 死亡者、感染者がまだ出ているが、医療ひっ迫の防止が肝なので、医療ひっ迫が軽減したら緊急事態宣言を解除した。つまり、ハンマー&ダンスを繰り返すことで、経済への配慮もしていたということがまず1点。 もう1点、世界の最大の行事であるオリンピックについて、当初、私は意見を言うべきではないと国会でも答えていました。ところが、6月になるとこの考えを変えなくてはいけない状況が出てきた。 7月には第5波、感染力の強いデルタ株が出てくる中で、夏休み、お盆、3連休というのが重なる。この状況を放っておけば、オリンピック開会式の前後には、間違いなく医療のひっ迫が深刻となり、緊急事態宣言を出さざるを得なくなると、我々専門家はほぼ確信していました。 結論から言えば、オリンピック開会式の10日前には緊急事態宣言を出さざるを得ない状況に実際になりました。我々専門家としては、オリンピック開催前後には、オリンピックをやらなくても、緊急事態宣言を出すほど医療がひっ迫、死亡者が出るということをわかっているのを言わないということでは、専門家としての責任を果たせるのか。我々が専門家として知り得たこと、知見、経験、考えを示すべきと考えました。 ただし、私たちはオリンピックスタジアムの中で感染が広がるということはそれほど考えていなかった。 しかし、緊急事態宣言を実際に出し、一般の人になるべく行動変容を要請しているときに、医療がひっ迫・崩壊しそうなのに、わざわざ観戦者を入れて開催することはどうなんですか? 合理性がありますか? このため、一番求められる方法が無観客です、と提案しました。 オリンピックをやめるとは、我々は提案するべきではないと思いました。そこは越権行為です。 なぜかというと、選手たちはずっと頑張ってきたわけですよね。仮に感染対策だけを考えれば、やめた方がベストかもしれないけれども、それを私たちは言うべきではないと思っていました。何年間も努力した選手たちの活躍の場を我々専門家が奪うことは、やってはいけないと思いました。テレビで観戦を楽しんでくだされば、という思いでした。
Clip.06パンデミックによって残された課題
○新たな取り組みは? 今回大変な思いをしなかった人はいないと思います。そういう中で政府の方でも例えば危機管理庁というのをつくったし、昔の国立感染症研究所と国際医療センターという2つの組織を統合し、日本版CDCをつくった。 それから次のパンデミックに備えて行動計画も、既に国でも地方でもつくっています。そうしたことについて私は評価していますが、これがしっかり実行されることを期待しています。 次のパンデミックに備えるためには、今、この感染が比較的落ち着いた時にしっかりと議論して、みんなのコンセンサスを取っておくべきテーマがいくつかあります。例えば医療のひっ迫という問題です。日本の医療は、例えば内視鏡や外科の手術がうまい、こういう質の面では世界で一流です。しかも今回、死亡者があれだけ少なかった。それでもなぜ医療のひっ迫が起こって、緊急事態宣言を4回出さなければならなかったか。 次もまた同じようなことが起こり得るわけです。今回やったことは限られたリソースを有効に活用するということでした。例えば、ベッド数には限りがある。急には増やせないので、コロナの患者さんを入れるために一般の診療を少し制限した、などです。しかし、有効な資源を最大に活用するだけでは乗り越えられないことがあり得る。そのためにはやっぱり医療供給体制のそもそものあり方というものを、しっかりと関係者の間で議論しておくことが必要ではないのかというのが1点目です。 それから、2点目は、実は今回、我々専門家が一番苦労したのは、疫学情報がデジタル化されていないため、内容も不十分だし、スピードも遅かった。その上、ファックスで送らなければならなかった。 台湾とかシンガポールとか韓国は2009年にあった新型インフルエンザH1N1のパンデミックの経験を踏まえて、かなりデジタル化しているんです。ところが日本は残念ながら、こうなってしまった。疫学情報のデジタル化というのは、今回のコロナの前からずっとパンデミックと関係なしに言われていたことなんです。ところが、これが期待されたスピードで進行していないのは、これは事実です。 それから3つ目はこのパンデミックという危機の状況が、短期間ならいいが、長期間続くと初期の不安というものが不満に変わってくる。しかも情報だけ多くなると、どうしても分断が起こりやすくなる。今回も起こった。 当時は8割、最低7割の接触を避けようということを安倍総理がおっしゃって、これについてもほとんど皆が何となく、この不安のために一体感みたいなのが出てきたと思います。ところが、第1回緊急事態宣言が終わると、まず人々が少し慣れてきて、もう一度やるのは嫌だという気持ちになりますよね。いろいろな情報が出てくる中で、さまざまな情報が流れるということで、中にはこっちの情報が正しい、こっちの情報はよくないということで、少し分断みたいになり、コミュニケーションがなかなかうまくいかなくなってくるんですよね。情報効果がなくなってきたというのは、そういうことも関係すると思います。次回これにどう対処するか、もう少し納得感が得られるにはどうしたらいいか、5類になるころからいろいろ議論しました。 受ける側はデータだけで人間が動くわけではなくて、それぞれ感情だとか価値観もあるわけですよね。国の大臣とか専門家が一方的にデータをもとに数字とグラフを中心に、一方的に説明するだけでは不十分。 相手側の考え、気持ち、価値観を聞いた上で共創的なダイアローグをしていけば、少しでも分断という現象が軽減するのではないのか。 そういう意味では、国のリーダーシップも専門家もマスコミなども関与してくれたり、一般社会が双方向の共創的コミュニケーションをどうつくっていくかというのは、紙に書いただけではダメで、今から試行錯誤をして、トライアンドエラーをしながらそういうシステムをだんだんつくっていくことが求められるのではないかと思います
Clip.07次のパンデミックに備えるために
○感染症・日本これからの課題 実はパンデミックとは独立して、いま日本の医療供給体制はかなり厳しいところに来ています。パンデミックがくればなおさら。今の日本の場合は小さな病院が多く乱立している。しかも診療報酬というものが決まっていて、ベッドが空いたままの状態でいることなんてできないんですよね。 対症療法じゃなくて、それは医療機関なども集中・統合・役割分担を明確にするというようなことを国も考えている。その辺のメリハリをつけた体制にしておくことがパンデミックにもいいし、国民の医療をこれから変化する医療に対応する方法だと思います。 医師は医学部6年間も教育を受けて、臨床研修もあるし、PCRの検査、このぐらいは誰でもできるはずなんです。 ところが今はどうしても専門医志向というのが強くて、国民は専門医を求めているんですよね。だって心臓の手術をしたら、何でもできる先生よりも心臓の手術に自信があるという先生に診てほしい。しかし、それと同時に一般の多くの高齢者、たくさんの病気を持っているわけです。これだけしか診られないという医者が今のところ多いわけだけど、もう少し裾野を広げて、一般の病気については診られるという医者の数をもっと増やさないと。その中で専門性をたてたっていいわけですけど、これはうまくバランスをとる必要があります。大学の医学部教育もそうだし、その後の医師の育て方、専門医制度のあり方なんかも関係すると思います。 医療のデジタル化に向けて 疫学情報は紙ベースでやってきた。特に感染症の方は、ファックスでやっていた。しかも、なかなか届かないから専門家の一部が直接各自治体の知っている人に電話して、こういうことをやっていたんです。これは大変なことですね。最初、クラスター対策というのは、後ろ向きの疫学調査とかいろいろやって、結構これは当初効果があった。しかし、保健所のマンパワーが限られているということと、デジタル化がなかったので、途中まではそれでいけたが、感染者が増えてくるとクラスター対策だけでは対処できなくなる。 ある東京の病院でCTスキャンをとった。北海道旅行してまた病気になると、すぐに(CTスキャンを)診られるほうがいいですよね。こういうシステムにはまだなっていないと思います。 同じ検査を何度もする、血液検査を何度もする、健診のデータと医療情報のデータが、また同じことを繰り返す。これが一人の個人のデータはどこの病院に行こうが、ワクチンを受けたのか、血液検査はどうだったのか、CTスキャンの結果どうだったのか、というのがわかればいいですよね。 それが日本は不足していたということです。
Clip.08流行が続く新型コロナウィルス。 インフルエンザと同じと捉えてよいのか?
○今も続く新型コロナウイルス 第8波になるにつれて、どんどん死亡者が増えているという話、それは一つファクトですよね。 もう一つ、インフルエンザと、それから新型コロナでの死亡者を示したものがこれで、2019年から2024年まで、黄色がインフルエンザによる死亡者。青がCOVID、今回の死亡者、これを見ると圧倒的ですよね。このことはファクトとして。致死率は下がってきています。特にオミクロン以降。しかし、死亡者の絶対数というものはインフルエンザの比ではなく、大きいということはファクトとしてみんな共有した方がいいんじゃないかと思います。 特に高齢者は一番リスクの高い、あるいは基礎疾患を持っている人は亡くなる可能性が高いので、注意をしてくださいということだと思いますね。 ○私たちに求められる心構えは? 残念ながら、次のパンデミックは起こると考えていた方がいいですね。それはなぜかというと、今までももう皆さんご承知のように、人口が増加して、人々の動きが地球上で増えて、それから森林の伐採がある、開発があって、人と動物の接触が増えてきた。あと、地球温暖化があって、蚊なんかがどんどん北の方にも入るようになってきている。それから大豪雨があったり、飢饉があると、余計にまた。あと戦争の問題もありますよね。戦争が起こると、感染症が出やすいんです。ポリオという病気はガザ地区ではずっとなかったが、今回イスラエルの影響で、なくなっていったポリオが出てきました。そういうことで、いろいろなパンデミックというか、感染症がはやる状況が出てきている。 その上に最近になっていろいろなエコシステムの研究者が発表した本があるんですけれど、この本は「なぜまたパンデミックが起こり得るのか」というのを分析した。いま言ったことに加えてです。動物というものを2つの種類に分ける。一つは野生動物、一つは家畜動物。野生動物の数がどんどん減ってきて、家畜動物の数が増えている。家畜というのは人間のそばにいて、狭いところで飼育する。動物もストレスになって感染症を発病して、それが人間に近いから感染する。というようなことも新たに言われ出しているので、これはやっぱりパンデミックが起こるか起こらないか、というよりはいつ起こるか、ということだと思う。一般の市民の人たちは今この時期に人と会うことを避ける必要なんか全くなくて、普通の生活をすればいい。私もしています。ただ、感染症はちょうど地震とか津波が来るのと同じように、もう我々の人類の生活の一部。 感染が広がったり、何か病気がはやっているときには、手洗いとか、マスクというのは普段もやるし、なるべく感染に強くなるため、免疫力を高めることですよね。それはしっかりと寝たり食事をしたり、時々運動できる範囲で運動をするということで、体力というか免疫力をつける。 またワクチンをつくる技術がさらによくなるでしょう。薬も前よりは開発するでしょう。あとは政治とか国際社会とか、地球温暖化にどう向き合うか、ということもやったらいいんじゃないかと思います。

- 沖縄県立中部病院
- 感染症内科・地域ケア科 副部長
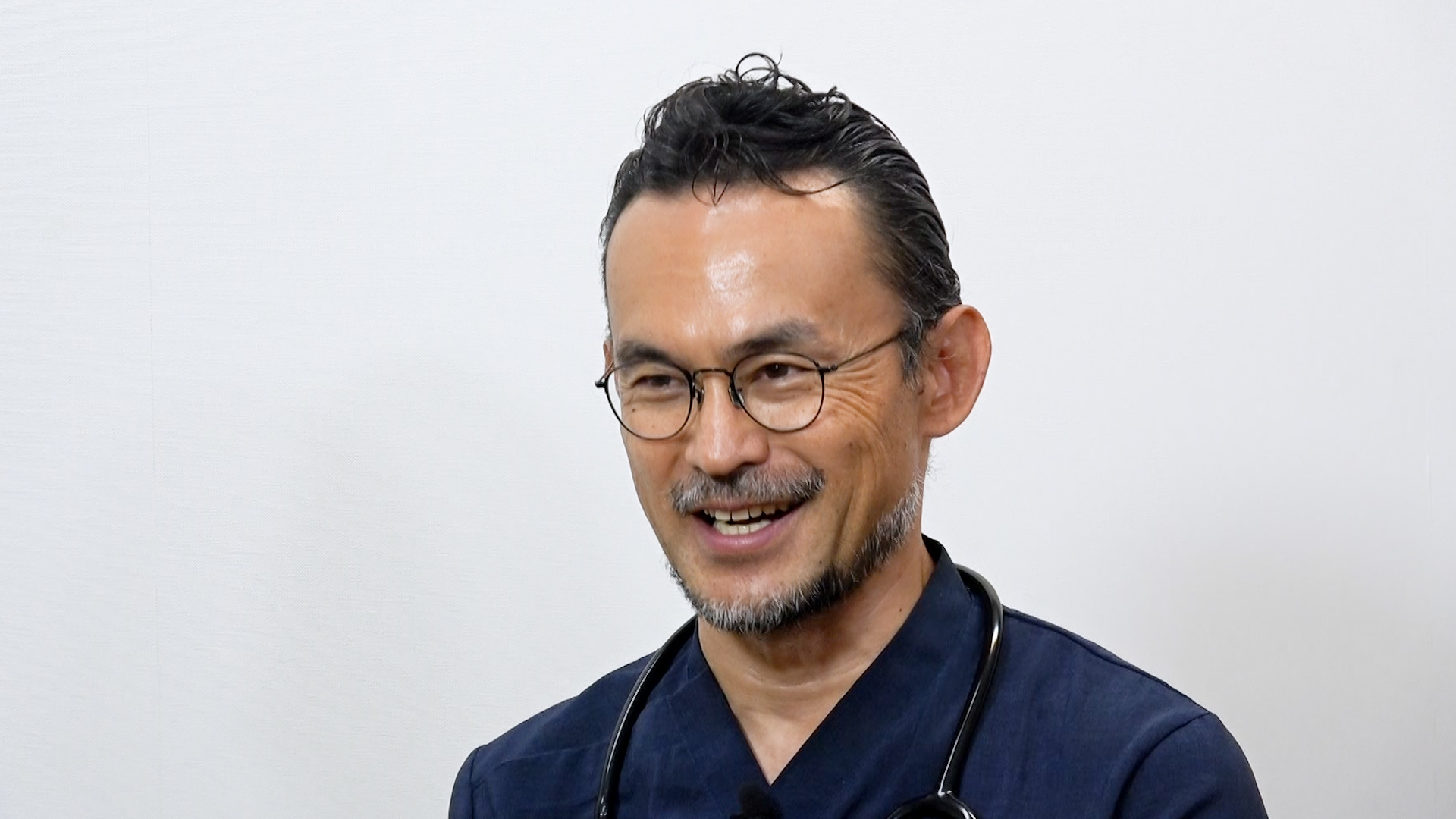
- 医療法人社団 悠翔会 理事長
- 訪問診療医
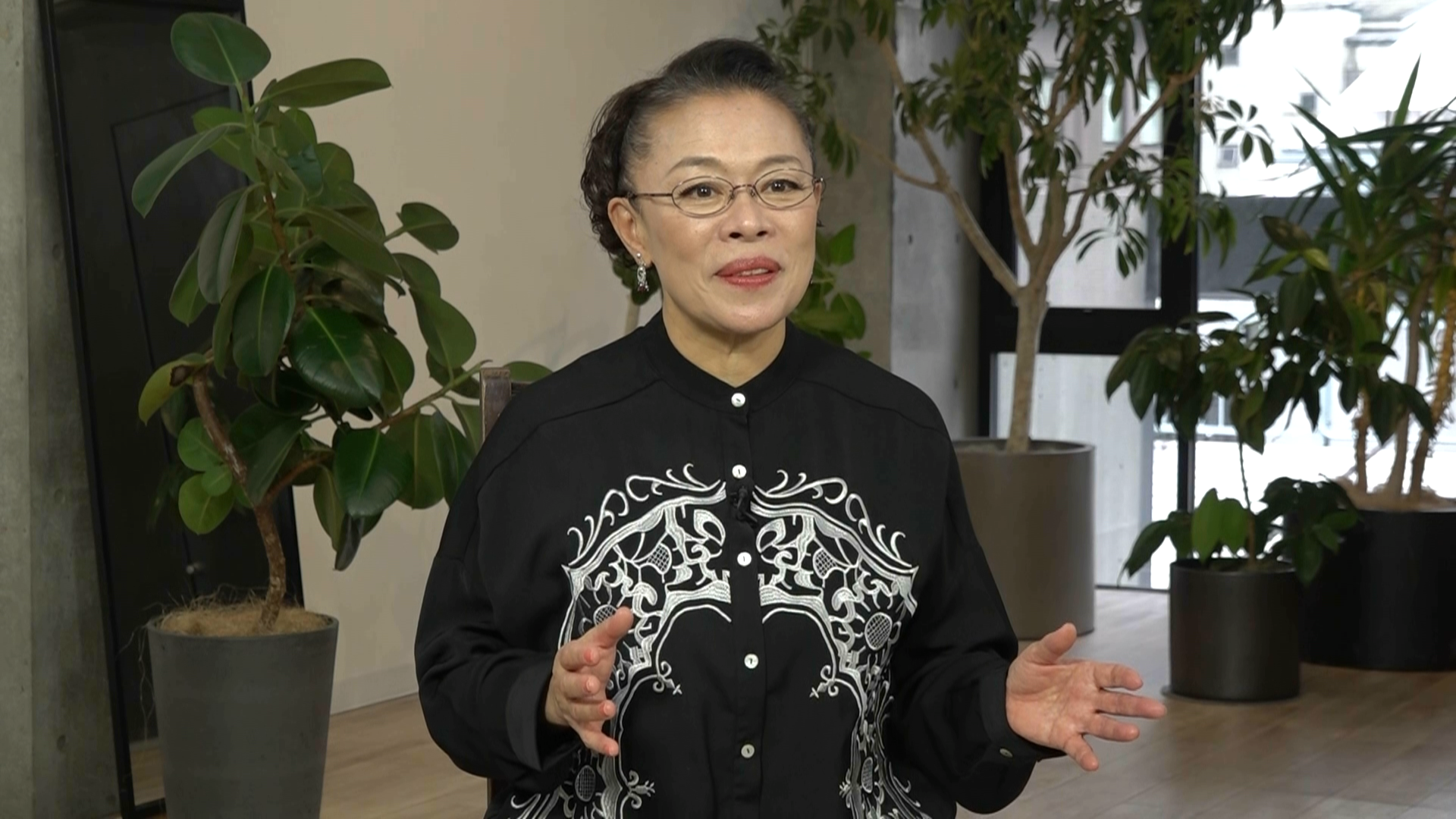
- 俳優・タレント
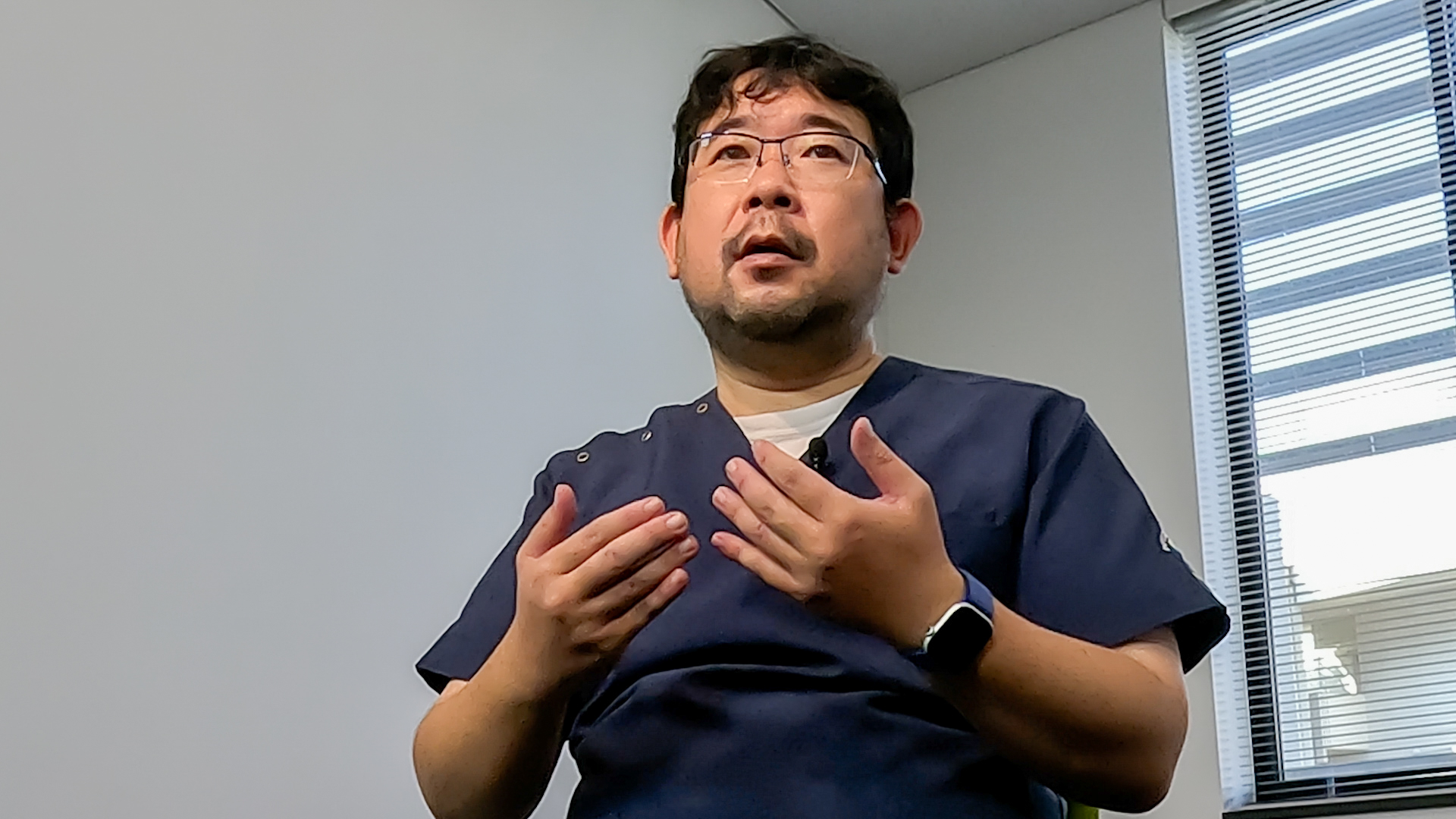
- 大阪大学医学部附属病院 感染症内科 診療科長
- 大阪大学大学院医学系研究科感染制御医学講座(感染制御学)教授

- 国際医療福祉大学医学部感染症学講座 代表教授
- 同 成田病院感染制御部 部長