新型コロナウイルスへの提言
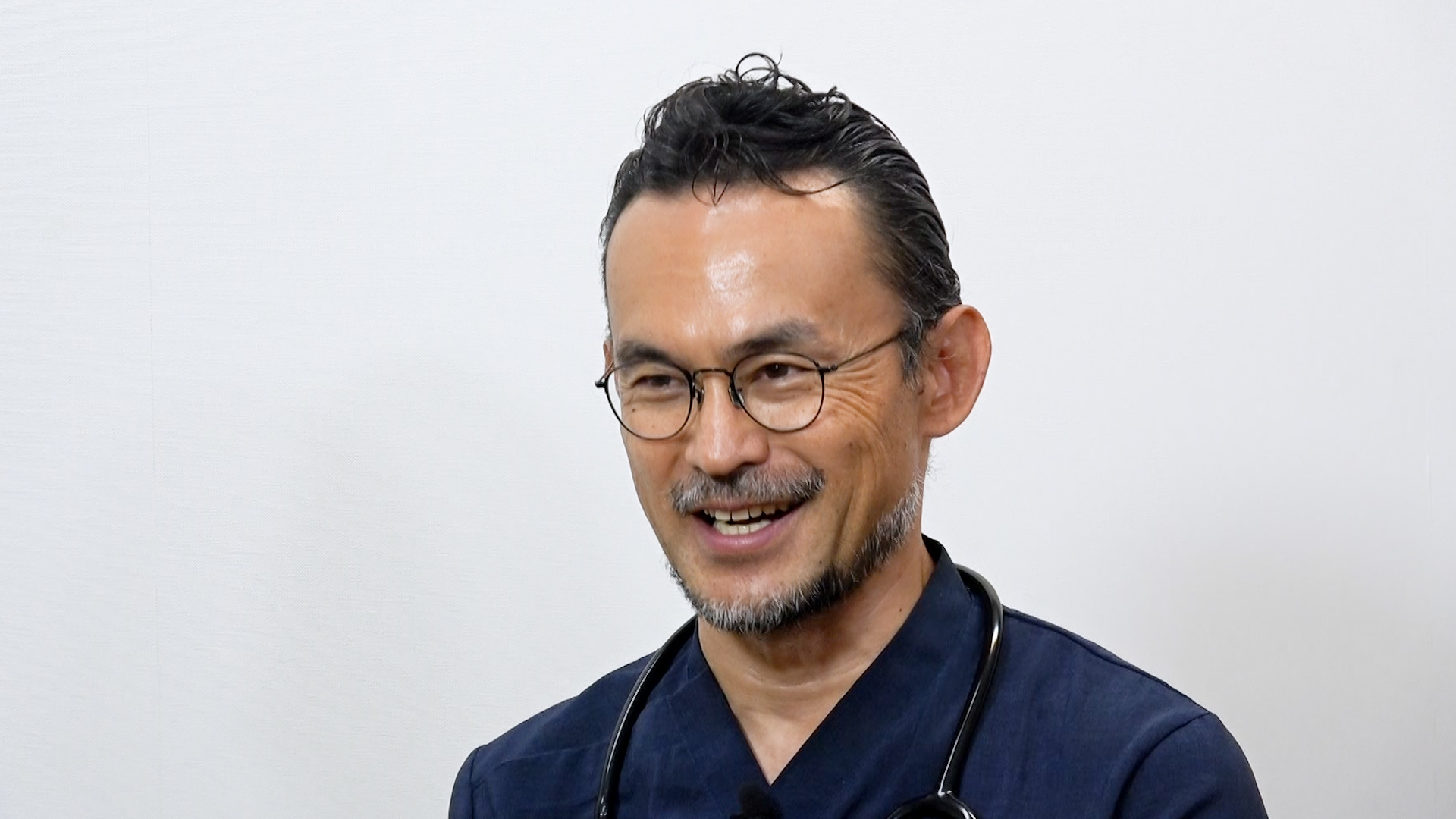
東京など都市部を中心に20以上の地域で訪問診療所を展開する佐々木淳 医師。2020年のパンデミック発生時は、ウイルスや対応策などについて海外から情報収集。適切に対応すれば安全と判断し、途切れることなく訪問診療を提供し続けた。一方、地域ではコロナ患者を受け入れない医療機関が続出。医療にたどり着けない患者があふれたことから、他の病院の患者を引き受けたり、自ら発熱外来を立ち上げ診療にあたってきた。「現在もコロナ感染は続き、高齢者施設ではクラスターも発生している」と指摘する佐々木医師。今回のパンデミックで、なぜコロナを診ない医療機関が多かったのか、なぜ人々はコロナで得たスキルや知識を捨ててしまうのか、その背景について語った。
ProfileView More
1973年 京都市生まれ。1998年 筑波大学医学専門学群卒業。社会福祉法人三井記念病院入職、内科、消化器内科を経て2003年 退職。2003年 東京大学大学院医学系研究科博士課程入学。2006年8月 在宅療養支援診療所を個人で開設、2008年に医療法人社団悠翔会として法人化。2010年には広域法人化し、東京、千葉、神奈川、埼玉など首都圏のほか、石垣島や与論島など島しょ部にも訪問診療クリニックを展開している。2020年からのパンデミックでは、いち早く感染予防対策をとり訪問診療を継続。さらに他の医療機関が診られない患者を、訪問医療や発熱外来で診療にあたった。
Profile
1973年 京都市生まれ。1998年 筑波大学医学専門学群卒業。社会福祉法人三井記念病院入職、内科、消化器内科を経て2003年 退職。2003年 東京大学大学院医学系研究科博士課程入学。2006年8月 在宅療養支援診療所を個人で開設、2008年に医療法人社団悠翔会として法人化。2010年には広域法人化し、東京、千葉、神奈川、埼玉など首都圏のほか、石垣島や与論島など島しょ部にも訪問診療クリニックを展開している。2020年からのパンデミックでは、いち早く感染予防対策をとり訪問診療を継続。さらに他の医療機関が診られない患者を、訪問医療や発熱外来で診療にあたった。
Clip.01「自宅で診る」準備から始まった
●訪問医としてパンデミックとどう向き合ってきたか コロナが「ダイヤモンド・プリンセス」が横浜に入ってきて、ちょっと怖いウイルスが日本に入ってきたかもしれないよという時に私たちが最初に考えたのは、そもそも「得体が知れない」というところが恐怖の本体だと思ったので、まず情報収集に努めました。ただ、日本国内から出てくる情報というのはなかなか限定的だったので、アメリカのCDCとかイギリスのNHSとか、公共機関が発信する最新の論文を常にキャッチアップして、それを翻訳してチーム内に伝えたり、他にも例えばジョンズ・ホプキンス大学とか、イギリスのロイヤルカレッジオブロンドンとか、こういった研究を積極的にやって発表してくれているところにもアンテナを立てて、それから国内の感染症の専門家とも定期的に意見交換しながら、例えば「自宅で感染が起こったらどうするか」とか、「施設の中で感染が起こったらどうするか」、あるいは「感染を予防するために効果的な方法は何なのか」みたいなことを「インフォグラフィック」を作って研究する事業者さんに配ったり、業界団体の新聞に投稿して皆さんにお伝えをしたりみたいな活動を当初はしていました。 在宅の患者さんたちが感染したら、きっとみんな厳しい状況になるんだろうな、ということで、まずは「感染を持ち込まないためにはどうすればいいか」みたいなことは考えましたが、同時に当時、感染症法上の取り扱いで、感染すると、基本的に保健所の指示に従わなければいけないという状況で、多くの方は隔離病棟ですよね、感染症病床に入院をさせられるということがありました。ただ、私たちの患者さんたちというのは、コロナに感染したとしても、積極的な治療があまり功を奏さないとか、あるいはしたとしても厳しい、むしろ厳しい状況になる方も多いので、患者さんたちの中には、「コロナは怖いけど、感染しても病院には行きたくない」という方が結構いらっしゃった。 私たちは、そうであれば「可能な範囲で自宅で診てあげる」という選択が提供できるように準備をしていこうということで、第1波の頃から法人の中でガイドラインを作ったり、ある程度ちょっとシミュレーションをしたりというようなことを重ねてきて、保健所と相談して、ほぼ自宅で最期まで診るというような経験もしてきました。 第1波の頃はまだ緊急事態宣言とか、みんなもきちっと守ってくれて、感染もそんなに拡大せずに済みましたけれども、第2波、第3波と感染の波はだんだん大きくなってきて、実際に在宅の患者さんとか高齢者施設の中でのクラスターというのも頻度が上がってきました。 その時にはまだワクチンはありませんでしたので、私たち自身がしっかり防御をしながら、施設の中で、あるいはご家族の中で感染が広がらないように「ゾーニング」をするとか、その手前である「(抗菌)コーティング」をするとか、そういったことを私たちの方でやっていました。 本来であれば、保健所の業務っていう部分もあるんですけど、クラスターとか起こってしまうと、保健所が一気にキャパシティーオーバーになってしまうので、そこは保健所と連携しながら、例えば残っている入居者さんの感染の有無を我々の方でチェックをするとか、あるいはそのゾーニングを私たちもさせていただくとか、そういった連携をしながら乗り切ってきたというのがあります。 その後、ワクチンが開発されて、高齢の方のワクチン接種が徐々に始まってきたというタイミングで、首都圏では感染爆発が起こって、ちょうど第5波の「デルタ株」と呼ばれる株が主流だったんですけど、その時は私たちの患者さんは実はワクチンが一通り打ち終わっていたので、そんなに感染のリスクにさらされていない状況だった。感染したとしても重症化しないというコンディションが確保できていたんですが、ただ、東京都という地域でコロナ病床が満床になってしまって、コロナの患者さんたち、感染して重症化する人たちが予想を超えて急速に増えたので、(地域の)病院のキャパシティーを超えてしまったんですね。救急車を呼んでも病院に運んでもらえない方が地域にあふれてきて。その時に私たちはこれまでのように定期的にお伺いした患者さんたちのコロナ対応だけではなくて、普段元気だけど今コロナ肺炎で苦しんでいるという方のお宅に医療支援に入るということになりました。 ●訪問診療で取り組んで来たこと 2021年の8月から東京都医師会との連携の中で、東京都内で発生するコロナの肺炎で支援が必要な中等症以上の方を自宅で診るというところを私たちの方で対応させていただいて、8月、9月の2か月間で800人ぐらいの方ですね、自宅で対処させていただきました。3分の1はいわゆる「中等症2」という、酸素飽和度が低くて、酸素吸入が必要なレベルの肺炎の方々だったんですけど、いずれも入院はできなくて、自宅に酸素濃縮機を配置して、食べられない人は点滴をして、投薬が必要な人はお薬を処方して、自宅で安全に回復できるか、あるいは入院の順番が回ってくるまで、私たちの方でケアをするということをさせていただきました。 コロナの患者さんの対応はその後も続いていまして、私たちは発熱外来もその後も続けていますし、自宅や施設、特に高齢者施設では今もクラスターは発生していて、そういった対応は今も続けていますが、ただ、今はワクチン接種が必要な方には行き届き、そしてコロナ感染した方には抗ウイルス薬という治療薬の選択もありますので、自宅や施設で治療が完結できる方がかなり増えてきています。 ただ、第4波、第5波の時というのはワクチン接種がまだ必要な方に行き届いていなかったこと、一回も打ったことがないという方がたくさんいらっしゃいましたし、治療薬がまだなくて、在宅で使えるお薬はステロイド、炎症を抑えるステロイドだけだったんですね。中和抗体薬(ちゅうわこうたいやく)というのがちょうど出てきた頃で、病院であればそれが使えるという話だったんですが、自宅ではそれはまだ使うことが許されていなくて、したがって「武器」もあまりなかったんですね。ただ、今はワクチンもあるし、薬もあるしということで、地域全体の対応力というのは非常に高まっていると思います。
Clip.02初期の「医療ひっ迫」はなぜ起きたのか?
●パンデミック初期に、地域で起きていたこと 第1波の時から「コロナに関してはうちは診ない」と。「発熱者は発熱外来のある病院に行ってください」っていう医療機関が圧倒的に多かったんではないかと思います。私たちは在宅医療機関なので、24時間、主治医としてその人を診るっていうことが制度上も立て付けられているっていうのもありますし、自分たちが関わった患者さんたちに、自分たちが主治医として責任を果たす道義的な責任もあると思っていましたので、ここは法人の中では誰も反対者はなく、自分たちでやっていこうってことでコンセンサスだったんですけど。 ただ地域では「発熱したんだけど、かかりつけ医が診てくれないので遠くの病院まで受診しなければいけない」とか言う方が結構おられました。ここの診療所も基本的には在宅メインのクリニックですけど、「地域で発熱者を診る外来がない」ということだったので、発熱外来はオープンして、発熱の方は受け入れるってことをやったんですけど、特に千葉のエリアは発熱外来に対する協力医療機関が非常に少なくて、ここのクリニックもですね、遠くから20キロとか30キロ向こうから車に乗って受診をされるっていう患者さんたちがピークの時にはもうたくさんおられて、そこの駐車場にずらっと車が並ぶってことが一時期は毎日のように起こってました。第4波、第5波ぐらいからですかね。最近はさすがに基本的にはどこの医療機関でもインフルエンザと同じ程度での対応で診てくれているという感じだと思いますけれども、本当に4波、5波、6波、その後1年ぐらいはそんな状況が続いていたんじゃないかと思います。 ●発熱外来が少なかった背景 未知の感染症だということで、これはいわゆる「ちまたの医療機関、地域医療機関が対応すべき疾患ではない」と考えた先生方もおられたと思いますし、あとはご自身も、例えばもう高齢なので「感染した時のリスクが高いので、できたら受けたくない」という方もおられたと思いますし、あとはその診療所の物理的な状況で、「ちっちゃな場所だし、発熱者を導線を分けることもできないので、普段診ている患者さんと発熱者を同じ場所で診られないから、うちでは診ることができない」とお断りされる先生もおられました。 例えば千葉だと、発熱外来に協力した医療機関が全体の20%ぐらいで、80%は発熱外来を開いていない、というか、発熱者を診てくれなかったんですね。ただ、当院ももちろん導線を分けることが全然できないんですけど、でも患者さんに、例えば駐車場で待っててもらって、車の中で外から診察をしてお薬を処方するとか、検査をするっていう形でやっていたので、工夫をすれば診られないことはないんだと思いますけど、そういう状況がありました。 ワクチンを打ってくれる医療機関も少なかったので、ワクチンが打てるというクリニックに長い行列ができたりとか、そういう状況は当初はこの辺でも見られました。 ●初期の医療ひっ迫が患者にもたらしたもの 自分がかかりつけ医だと思っていた医療機関にかかろうとすると、「かかりつけ医ではないから診られません」とか言われたり、ワクチンに関しても「かかりつけではないのでご提供できませんと言われたり…してしまったんですけど」とご紹介されて来られる方もおられましたし、「熱が出たんだけど、どうしましょう?」っていった時に、「うちは診られないんで保健所に相談してください」って言われてしまうと、やっぱり見放されたような感じはするんだと思うんですよね。仮に自分が診られないんだとしても、状況を判断してアドバイスをしてあげるとかできると思うんですけど、そういったことに関して「うちの仕事ではない」という態度を取られたということで、発熱で往診した患者さんたちから、自分のこれまでのかかりつけ医に対する失望というのを聞くこともたびたびありました。 実は東京はもともと医療とか社会サービスにつながってない方が結構おられて、そういった方は、でもコロナで本当に苦しくなると、「保健所に連絡すればいいんだ」と言って保健所に連絡をして、初めて(訪問診療の)サービスにつながったという方も中にはいらっしゃいますが、ただ一方で「超過死亡」が非常に大きくて、必要なサービスが受けられずに亡くなった方は当然おられたと思います。
Clip.03「合理的な医療提供体制」をつくる
●“平時”に「合理的な医療提供体制」をつくる重要性 第5波のコロナ報酬の時は、いわゆる「特別な加算」はほとんどなかったので、コロナの患者さんたちを診て、休日夜間のバックアップも含めて、その人たちが元気…安全な状況になるか、できるまでフォローしていくことになるんですけど、そこの部分に対する診療面の“評価”はないので、結局かなりの赤字になって、その赤字を補填するためにクラウドファンディングするみたいなこともやりましたけど、でもそこから先は、例えば東京都の場合、夜のコロナ往診に一回10万円の加算がつくとか、ちょっと行き過ぎというか、やり過ぎなところも明らかにあって。 やはり合理的な医療提供体制というのは日頃からきちんと構築しておかないと、こういうときにすごく付け焼き刃で仕組みを作るというのは高くつくし、結局それは地域医療の先生たちが…ということではなくて、往診専門会社が「事業」として受託するみたいな形になっちゃうと、結局、地域には何もレガシーが残らないという。その辺はもうちょっとやりようはあったかなという気がしますね
Clip.04「5類移行後」の世界で起きていること
●「5類移行後」の世界 コロナの感染死亡者はその後1桁多いというか、すごいたくさん亡くなっていますし、今回も感染拡大がかなりひどくなってからようやくニュースになったりもしますけれども、社会の関心というかメッセージとしては、「もうコロナは気にしなくていいから」という感じのメッセージで、多分伝わったんだと思うんですよね。 これまでの経済活動とか、あるいはいわゆる不要不急を控えるみたいな抑圧から解放されるのは、それはそれでいいんですけど、「コロナが終わった」というのは、それはそうではないし、やっぱり「感染拡大しているときは気をつけないといけない」とか、「必要な人がワクチンをちゃんと打たなきゃいけない」とか、「体調が悪い人は人と会うことは避けなければいけない」とか、コロナの数年間で私たちが身につけたはずのさまざまなスキルや知識を「5類です」と言った瞬間に「ポイッ」って投げ捨ててしまった人が思いのほかたくさんいて、それはとても残念というか。だからもうちょっとその「3類」だ「5類」だっていう「0か1か」ではなくて、コロナとどう向き合っていくのかみたいなことを、もうちょっとちゃんと丁寧に伝わるとよかったんじゃないかなと思いますね。 当初、例えば第1波、第2波のときは、感染して亡くなるリスクの高い人たちを「感染から守るためにみんなで協力しようよ」みたいな雰囲気があったと思うんですけど、最近はむしろそうではなくて、「どうしてそういう人たちのために私たちが我慢しなきゃいけないんですか?」ということを、SNSとかでは公然と発信する人たちが増えてきて、それに同調する人たちも本当にすごい数いて、我々がスマートに進化したというよりも、なんだかちょっと野蛮になった感じがするかなと。「自分さえよければ」というような人も増えてきたような気がしますね。 それは何かやっぱりみんなそれなりに困っていて「他人を思いやったりするほどの余裕がないよ」という意味なのかもしれませんけど。「俺だって困っている」っていう。 「特別な配慮をしろ」ということ自体は難しいのかもしれないけれど、ただ、それが「特別な配慮」じゃなくて「普通の配慮」となっていくのが、おそらく我々にとって進化だと思うんですけれども、そこでもなかなかやっぱり簡単ではないんだなという感じがします。
Clip.05次のパンデミックに備えるために 一人一人にできること
●あらわになった日本の医療の“特殊性” パンデミックっていう巨大な感染の波、たくさんの方が感染した時に、感染で苦しんでいる状況の中で、例えば「発熱外来がある中核の病院だけでそれを対処せよっていうのは無理なんだろう」って、みんな分かると思うんですよね。発熱外来対応してくれていた中核病院の中では院内感染が起こって、病棟が閉鎖になったりみたいなことも起こっていて、「なんでそんなことやってるんだ!」っていう社会の批判が、そういった病院に「きちんと感染対策していたのか!」とか、そういった病院で働いている専門職に対して地域住民の差別があったり、例えば、看護師さんの子どもが保育園に預けられないみたいなことも一時ありましたけど、結構厳しい状況だったと思うんですね。 最前線でプライマリ・ケアを担う私たちが、まずは地域住民の啓発をして、正しい知識を持ってもらう。それから、正しい予防行動と正しいワクチンや治療に対する知識を持ってもらう。で、その上で、もし万が一感染してしまった場合には、まず私たちが診断をして、可能な範囲で治療して、入院ができないんだったら自宅でそれを診る。これって別に私たちできると思うんですね。 完全に未知のウイルスだったらできないかもしれないけど、パンデミックが始まってすぐに、これがコロナウイルスの一種だということが分かったので。であれば、いわゆる普通の感染防御と、それからいわゆる「ユニバーサルプレコーション」(普遍的予防策)をきちんとやれば、自分たちが感染から身が守れるということは分かっていたわけですから、そういったことを学んで医師免許、看護師免許を取っているはずなので、やれるはずなんですよね。 だけど、やらない理由を探して、みんなやらなかったっていうのは、ちょっとそのプライマリ・ケアというか、地域医療の担い手としては責任の放棄だったんじゃないかなと私は個人的には思います。 やっぱり地域の中で仕事をしていく上では、最低限やっぱり地域のための仕事をしなければいけないし、緊急事態だというのに「安定した持病の患者しか診ませんよ」。そこら辺で熱が出ている人がいるのに「私は知りませんよ」というのは、これはちょっといわゆる地域医療機関としてはあるべき姿ではないんだというふうに思いました。また同時に、日本の地域医療の特殊性というか、基本、海外はプライマリ・ケア医療機関が第一線で地域を守る、地域住民を守るという、そういうフレームワークを組みましたけど、日本はそうではなくて、医療対応力の強い、いわゆる高度急性期病院を中核拠点に据えて、変な話、「開業医の先生たちはできなければやらなくてもいいです」という、いわゆる病院中心の医療システムというのが、まさにこういった時にも同じような考えで動かされていて、これは本当に日本の特殊性だなというふうに同時に感じました。 ●プライマリ・ケアが果たすべき役割 やはり一番は、プライマリ・ケアの体制というのを、もうちょっと私たち強固にしないといけないなと思いますね。その地域を守る、医療を守るための最前線というのは、病院ではなくて私たちプライマリ・ケア医だと思うので、私たちがしっかり前線を守り、前線を守り切れなかった時に、最後の砦として病院が機能するって。これはパンデミックだけじゃなくて、慢性疾患もみんなそうだと思うんですね。 特にパンデミックは、地域の医療だけでは対処できない部分もありますし、「いろんな機関が連携していかなきゃいけない」ってなった時に、やっぱり「自分だけ診たい範囲だけ保険診療します」ではなくて、やっぱり保健所とか市役所とか、あとは消防とか救急とか、いろんなところと連携しながら協働できる体制を普段からとっておく必要があって、その辺が今回は全く機能していないっていうのが露呈したんだろうと思うんですよね。 日本の医療はこのコロナ禍以前からですけど、基本的にはたくさんの専門医がいて、患者さんたちは「フリーアクセス」が保障されていますが、自分の病気に最適なドクターを自分で見つけなければいけないんですね。専門診療と急性期病院を中心に、日本の医療ってこれまで動かされてきたと思いますけど、ただ、高齢化で複数の病気を持っている方もたくさんおられますし、そもそも何か起こった時にどこにかかればいいのかを自分で考えるって、やはりなかなか難易度が高いので、そういった時にまず誰かに身軽に気軽に相談できる身近なかかりつけ医というのはやはり必要なんだと思うんですね。かかりつけ医が機能することで、病気ごとに主治医を持つという非効率を解消することができますし、そこから出てくる診療のムラとか無駄とか、あとは多剤併用とか、薬が多すぎるみたいな問題も自ずと解消すると思うんですよね。 ただ、日本の医療体制そのものが、たくさんの専門の先生たちの分業で作られてきたという歴史があるので、ここをドラスティックに急に大きく変えるっていうのも難しいんだと思います。こういうことはいつでも起こりうるんだってことを今回私たちは認識をしたので、最低限の資材は常に院内に配備をする、何か起こった時にこういう形であれば対処ができる、あるいは感染症の患者を診る時に、こう動線を工夫すれば、うちのクリニックでも発熱者を診れるとか、そういったことは調整する必要があると思いますし、あとは高齢の患者さん、基礎疾患のある患者さん、あるいは高齢者が集住している住宅などを診る立場にある先生方は、もしこういうことが起こったらどうしようかっていうシミュレーションを常にして、何か起こった時にきちんと対処ができるようにしてなければいけないんじゃないかなと思います。 ●私たち一人一人に問われていること パンデミックというのは、医療機関だけで対処する、国や行政機関だけで対処できるものではなくて、やっぱり私たちのコミュニティを構成する私たち一人一人のリテラシーというか、私たちのしなやかさというのが問われているというところだと思うので、なのでこの振り返りの中では、私たち自身、一人一人の、こういった事態に対する考え方みたいなのもすごく大事なのではないかなと思います。 例えばコロナが3類から5類に変わったタイミングで、「もはやそんなものはなかったんだ」って、「いまだにマスクをしているのか?」とか、「ワクチンなんか必要ない」とか、何となくちょっとそういうよくわからない情報がまた流れてきて、それに影響される方も増えてきて。 高齢者施設においても、今もあちこちでクラスター起こっているんですけど、「こんな時にはこういう風に対処するんだよね」ってことを知っていたはずなのに、かなりユルユルな対応をしてドバっと広がってしまう施設があったりとか、逆に、「いま感染広がっていないのに面会制限しても意味ないんじゃないですか?」みたいなことをいまだにやっているところもあるんですよね。 例えば、この感染が拡大してきたら、なるべく人混みを避けるとか、行かなきゃいけないんだったらマスクを装着するとか、体調が悪いときは人に会わないとか、感染が疑われるんだったら、自分で調べられる人は調べて、感染してたら当然仕事とかイベントは避けるとか、「当たり前のこと」をみんながちょっとずつしていくだけでも、実は感染を抑えられて医療機関がキャパシティオーバーになることは当然ないんだと思いますけど。それをきちんと教育するのも、おそらくかかりつけ医の大事な仕事で、かかっている先生から正しい知識を教えてもらうということがとても重要で、だからコロナのワクチンに関しても、もう5類だからという理由で打つ人がすごく減ったんですけど、でもやっぱりインフルエンザに比べてまだまだリスクが高いんですよとか、打っておいた方が入院とか死亡のリスクは明らかに下がるんですよってことを丁寧に伝えると、「あ、じゃあ打っておこうか」と皆さんおっしゃるんですよね。だけどそのプロセスがないと、SNSの情報とか影響を受けてしまうので、まあ、そのインフォデミック対策っていうのが、このパンデミックの時にはとても重要で、自分のかかりつけ医に聞けるっていう関係性はやっぱりそこでも重要なのかなと思いますね。 これから先、おそらくパンデミックはかなり高い頻度で繰り返していくことになるんだと思いますけど、その都度同じような騒動ではなく、2回目、3回目は5類になったコロナを受け止めるような感じで落ち着いて見れるような体制をやっぱりちょっと地域ごとに作っていく必要があるんだろうと思います。
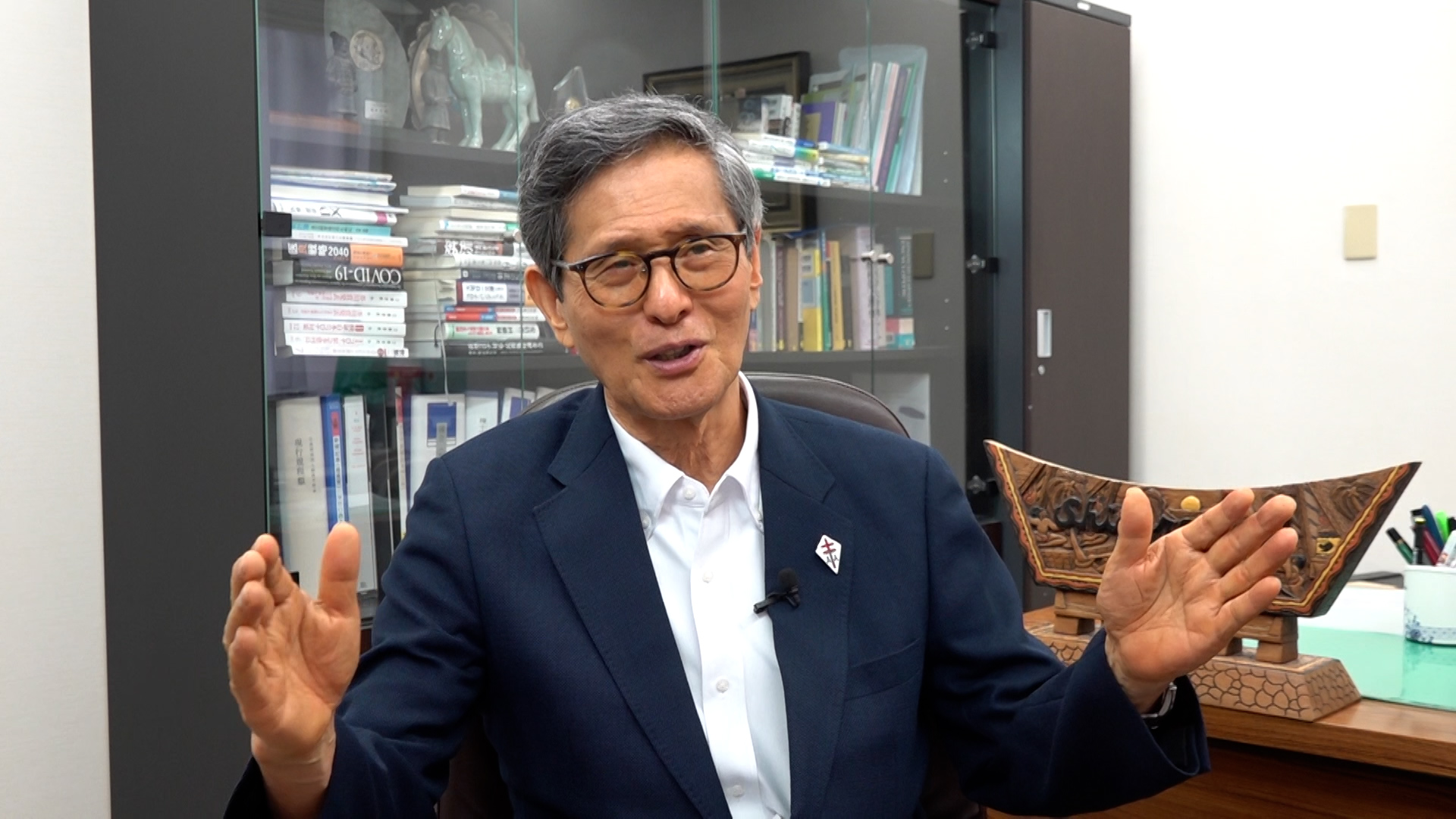
- 新型コロナウイルス感染症対策分科会 元会長
- 公益財団法人結核予防会 理事長

- 沖縄県立中部病院
- 感染症内科・地域ケア科 副部長
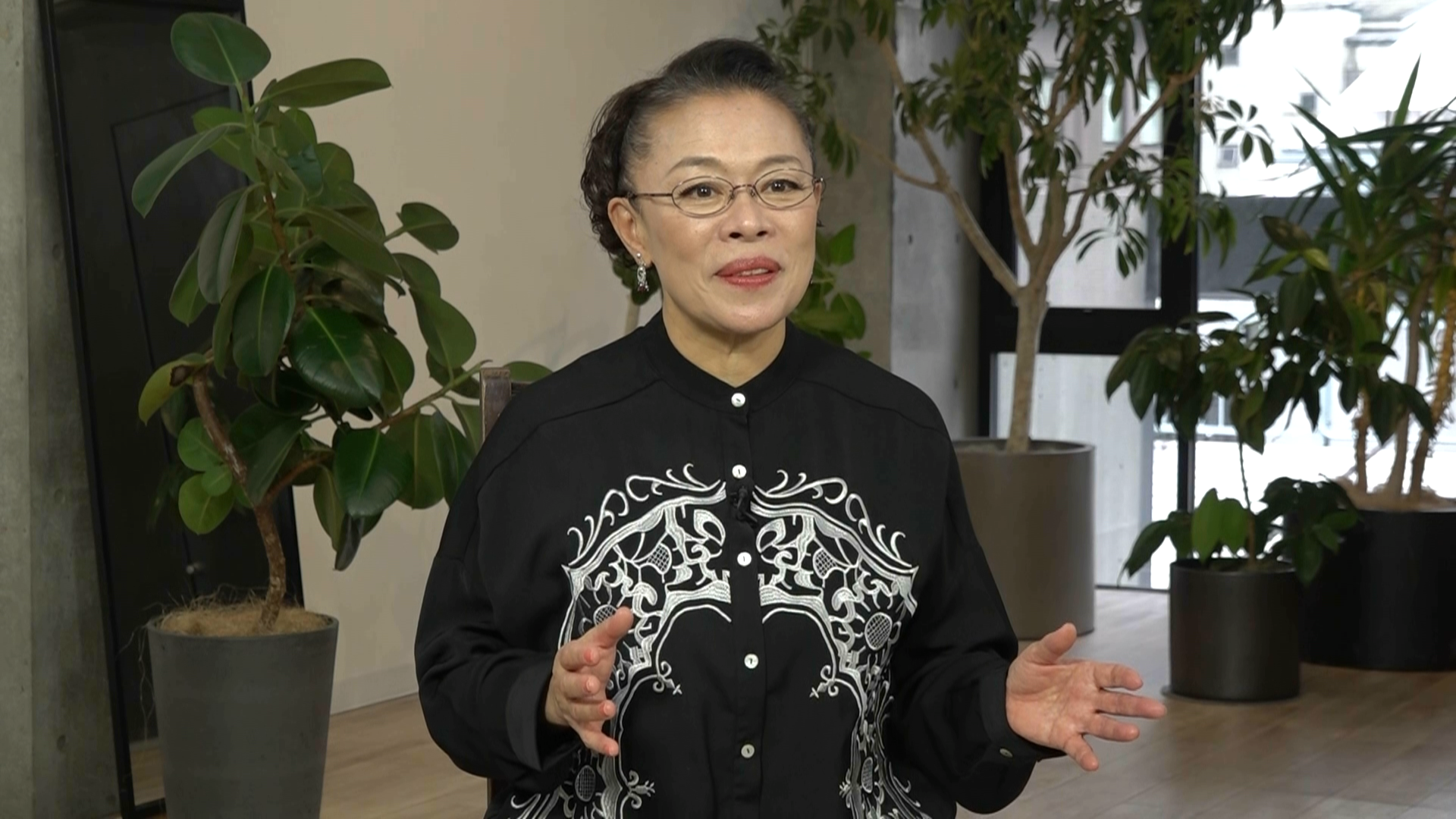
- 俳優・タレント
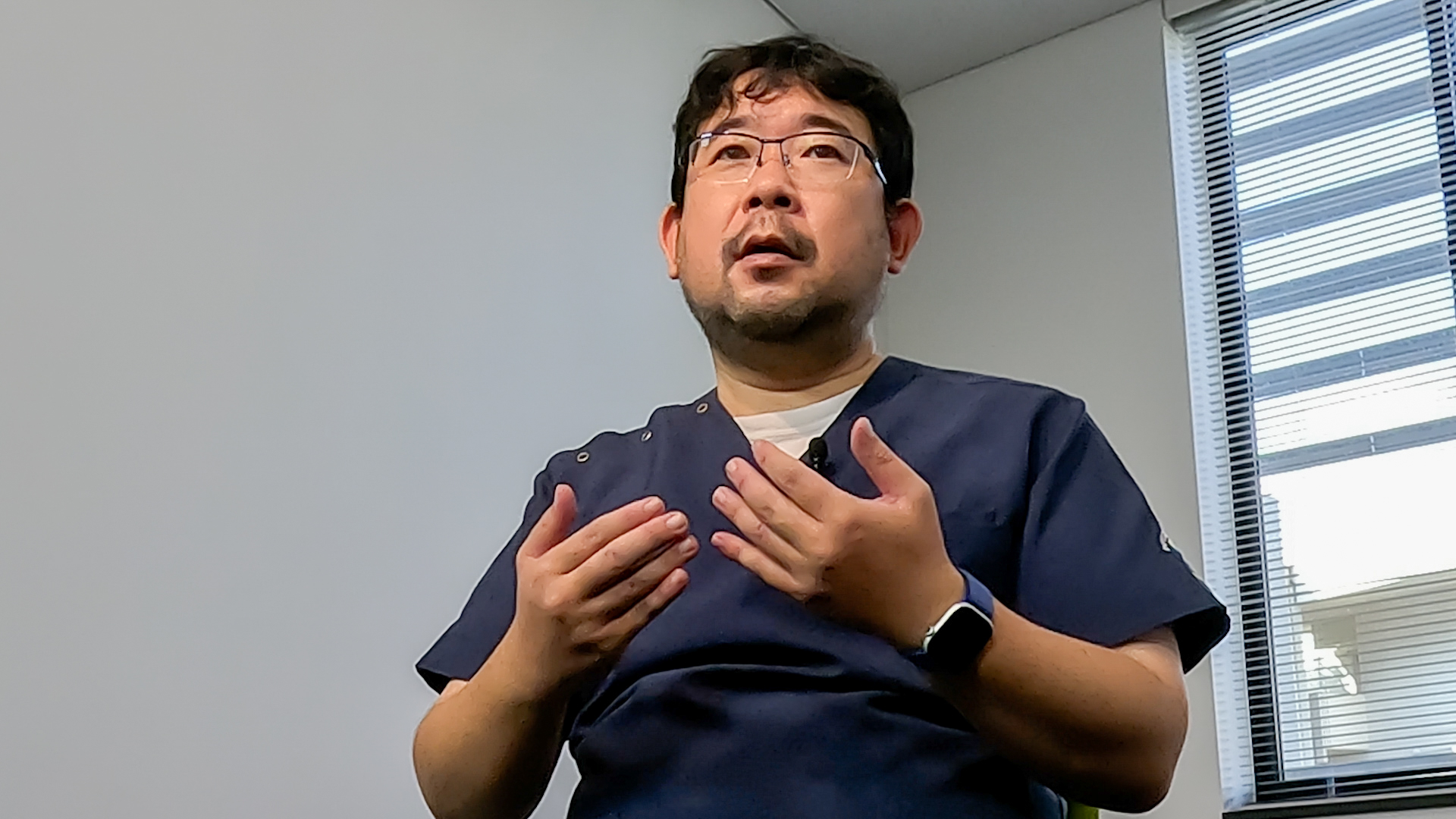
- 大阪大学医学部附属病院 感染症内科 診療科長
- 大阪大学大学院医学系研究科感染制御医学講座(感染制御学)教授

- 国際医療福祉大学医学部感染症学講座 代表教授
- 同 成田病院感染制御部 部長